不動産購入や建築計画を進める際、「位置指定道路」や「私道」という言葉を目にすることがあります。これらの道路形態は、建築基準法や土地の利用に大きな影響を及ぼすため、正確な理解が必要です。本記事では、位置指定道路と私道の違いや、それぞれのメリット・デメリット、申請手続きの流れについて詳しく解説します。これから土地を購入したり、建築を計画している方は、ぜひ参考にしてください。

1. 位置指定道路と私道の基礎知識

1-1. 位置指定道路とは?

位置指定道路とは、建築基準法第42条第1項第5号に基づき、特定行政庁(市区町村など)からその位置の指定を受けた私道のことを指します。この指定を受けることで、私道でありながら建築基準法上の「道路」として認められ、接道義務を満たすことが可能となります。
■ 位置指定道路の概要
建築基準法では、建築物の敷地は幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならない(接道義務)と定められています。位置指定道路は、この接道義務を満たすために、私道を特定行政庁から道路としての位置指定を受けたものです。これにより、建築物の建築が可能となります。
■ 公道・私道との違い
一般的に道路は、公道と私道に分類されます。公道は国や地方公共団体が所有・管理する道路であり、誰でも自由に通行できます。一方、私道は個人や法人が所有・管理する道路であり、通行に制限がある場合があります。位置指定道路は私道の一種ですが、特定行政庁からの位置指定を受けることで、建築基準法上の道路として扱われます。
■ 位置指定道路の管理と注意点
位置指定道路は私道であるため、その管理や維持は所有者の責任となります。具体的には、道路の補修や清掃、通行権の設定などが挙げられます。また、位置指定道路に面する土地を購入する際は、通行権や管理責任について事前に確認することが重要です。
位置指定道路は、建築物の建築を可能にするための重要な要素ですが、その管理や維持には注意が必要です。土地の購入や建築を検討する際は、位置指定道路の有無やその管理状況を十分に確認しましょう。
■ 位置指定道路の概要
建築基準法では、建築物の敷地は幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならない(接道義務)と定められています。位置指定道路は、この接道義務を満たすために、私道を特定行政庁から道路としての位置指定を受けたものです。これにより、建築物の建築が可能となります。
■ 公道・私道との違い
一般的に道路は、公道と私道に分類されます。公道は国や地方公共団体が所有・管理する道路であり、誰でも自由に通行できます。一方、私道は個人や法人が所有・管理する道路であり、通行に制限がある場合があります。位置指定道路は私道の一種ですが、特定行政庁からの位置指定を受けることで、建築基準法上の道路として扱われます。
■ 位置指定道路の管理と注意点
位置指定道路は私道であるため、その管理や維持は所有者の責任となります。具体的には、道路の補修や清掃、通行権の設定などが挙げられます。また、位置指定道路に面する土地を購入する際は、通行権や管理責任について事前に確認することが重要です。
位置指定道路は、建築物の建築を可能にするための重要な要素ですが、その管理や維持には注意が必要です。土地の購入や建築を検討する際は、位置指定道路の有無やその管理状況を十分に確認しましょう。
1-2. 私道との違いと共通点

「位置指定道路」と「私道」は、いずれも個人や法人が所有する道路であり、共通して以下の特徴を持ちます。
・所有者が個人または法人:どちらも国や自治体ではなく、民間の所有者が存在します。
・管理・維持は所有者の責任:道路の補修や清掃などの維持管理は、所有者が行います。
・固定資産税の課税対象:道路部分も所有者の資産として、固定資産税が課される場合があります。
しかし、「位置指定道路」は「私道」の一種でありながら、建築基準法上の「道路」として特定行政庁から指定を受けたものです。この指定により、以下のような違いが生じます。
違い
・法的な位置づけ:位置指定道路は、建築基準法第42条第1項第5号に基づき、建築基準法上の「道路」として認められます。一方、一般の私道はこの指定を受けていないため、建築基準法上の「道路」とは見なされません。
・建築の可否:位置指定道路に2メートル以上接している土地は、建築基準法上の接道義務を満たすため、建物の建築が可能です。しかし、一般の私道に接しているだけでは、建築が制限される場合があります。
・通行権の扱い:位置指定道路は、建築基準法上の道路として認められているため、原則として通行が許可されています。一方、一般の私道では、所有者の許可がなければ通行できないことが多く、通行権の設定が必要となる場合があります 。
このように、位置指定道路は私道でありながら、建築基準法上の「道路」としての機能を持つ特別な私道です。土地の購入や建築計画を進める際には、接している道路が位置指定道路かどうかを確認し、その法的な位置づけや管理状況を把握することが重要です。
・所有者が個人または法人:どちらも国や自治体ではなく、民間の所有者が存在します。
・管理・維持は所有者の責任:道路の補修や清掃などの維持管理は、所有者が行います。
・固定資産税の課税対象:道路部分も所有者の資産として、固定資産税が課される場合があります。
しかし、「位置指定道路」は「私道」の一種でありながら、建築基準法上の「道路」として特定行政庁から指定を受けたものです。この指定により、以下のような違いが生じます。
違い
・法的な位置づけ:位置指定道路は、建築基準法第42条第1項第5号に基づき、建築基準法上の「道路」として認められます。一方、一般の私道はこの指定を受けていないため、建築基準法上の「道路」とは見なされません。
・建築の可否:位置指定道路に2メートル以上接している土地は、建築基準法上の接道義務を満たすため、建物の建築が可能です。しかし、一般の私道に接しているだけでは、建築が制限される場合があります。
・通行権の扱い:位置指定道路は、建築基準法上の道路として認められているため、原則として通行が許可されています。一方、一般の私道では、所有者の許可がなければ通行できないことが多く、通行権の設定が必要となる場合があります 。
このように、位置指定道路は私道でありながら、建築基準法上の「道路」としての機能を持つ特別な私道です。土地の購入や建築計画を進める際には、接している道路が位置指定道路かどうかを確認し、その法的な位置づけや管理状況を把握することが重要です。
2. 位置指定道路のメリットと法的リスクを伴ったトラブル事例
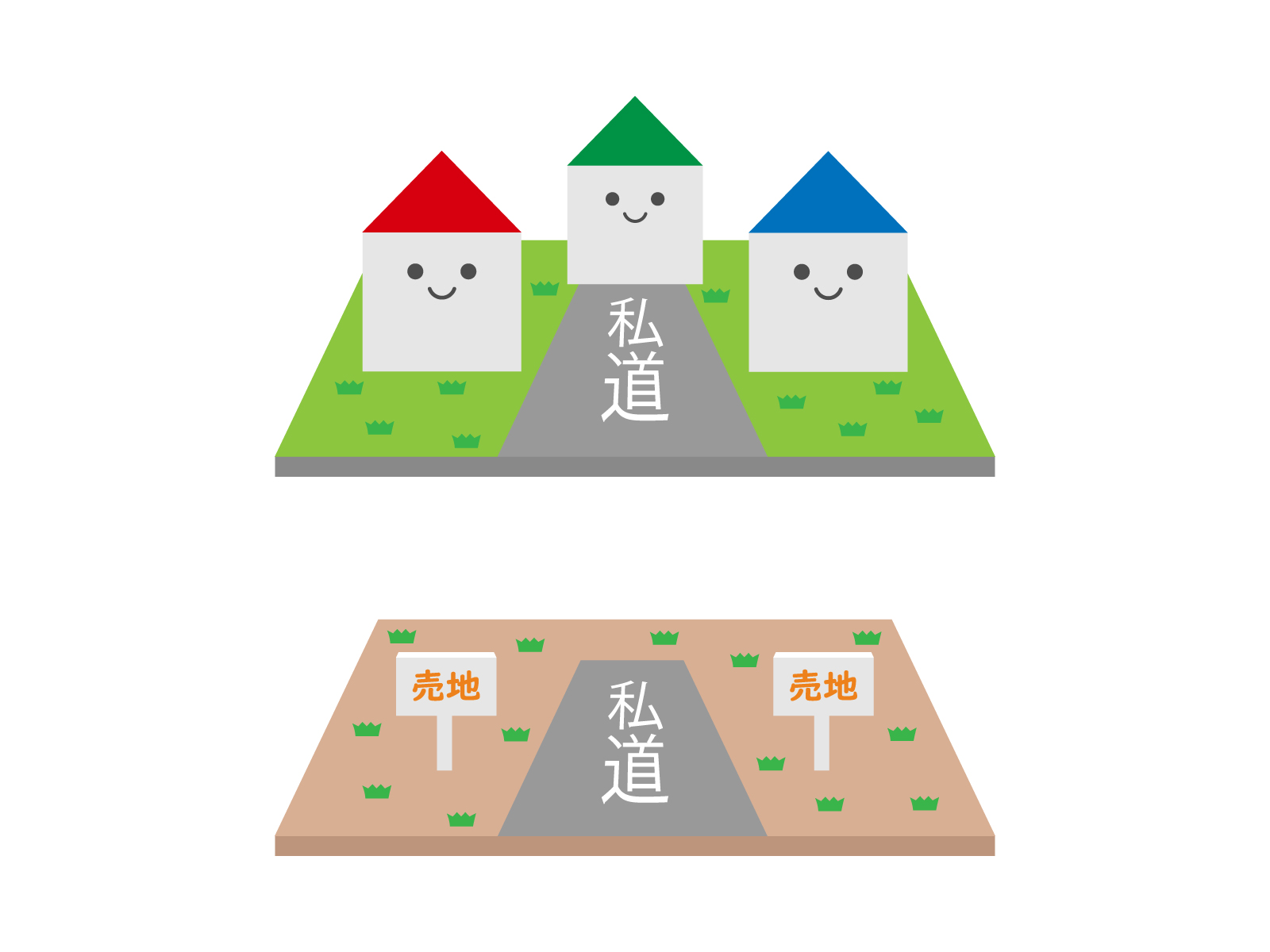
2-1. 位置指定道路のメリット

位置指定道路は、建築基準法上の「道路」として特定行政庁から指定を受けた私道であり、以下のようなメリットがあります。
1. 建築基準法の接道義務を満たしやすい
建築基準法では、建築物の敷地が幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならないと定められています。位置指定道路はこの要件を満たすため、建築確認申請のみで新築や建て替えが可能となります。
2. 土地の有効活用が可能
位置指定道路を設けることで、奥まった土地や旗竿地など、従来は建築が難しかった土地でも建築が可能になります。これにより、土地の有効活用が促進され、不動産の価値向上にもつながります。
3. 分譲開発における利便性
開発業者が複数の宅地を造成する際、すべての敷地を公道に接道させるのは難しい場合があります。位置指定道路を内部道路として設けることで、効率よく複数区画を確保でき、分譲可能な土地面積を最大化できます。
4. プライバシーと安全性の確保
位置指定道路は私道であるため、交通量が少なく、静かな住環境を提供します。これにより、プライバシーの確保や子供・高齢者の安全性が高まります。
5. 不動産価値の維持・向上
位置指定道路に面している土地は、建築が可能であるため、不動産の価値が維持されやすく、将来的な売却時にも有利となります。
これらのメリットを踏まえると、位置指定道路は土地の有効活用や不動産価値の向上を図る上で有効な手段となります。ただし、維持管理や通行権の設定など、注意すべき点もあるため、導入を検討する際は専門家と相談することをおすすめします。
1. 建築基準法の接道義務を満たしやすい
建築基準法では、建築物の敷地が幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならないと定められています。位置指定道路はこの要件を満たすため、建築確認申請のみで新築や建て替えが可能となります。
2. 土地の有効活用が可能
位置指定道路を設けることで、奥まった土地や旗竿地など、従来は建築が難しかった土地でも建築が可能になります。これにより、土地の有効活用が促進され、不動産の価値向上にもつながります。
3. 分譲開発における利便性
開発業者が複数の宅地を造成する際、すべての敷地を公道に接道させるのは難しい場合があります。位置指定道路を内部道路として設けることで、効率よく複数区画を確保でき、分譲可能な土地面積を最大化できます。
4. プライバシーと安全性の確保
位置指定道路は私道であるため、交通量が少なく、静かな住環境を提供します。これにより、プライバシーの確保や子供・高齢者の安全性が高まります。
5. 不動産価値の維持・向上
位置指定道路に面している土地は、建築が可能であるため、不動産の価値が維持されやすく、将来的な売却時にも有利となります。
これらのメリットを踏まえると、位置指定道路は土地の有効活用や不動産価値の向上を図る上で有効な手段となります。ただし、維持管理や通行権の設定など、注意すべき点もあるため、導入を検討する際は専門家と相談することをおすすめします。
2-2. 位置指定道路の法的リスクとトラブル事例

①所有権・通行権の課題
位置指定道路は見た目は公道のようでも私道であり、所有者が個人・企業である点に注意が必要です。複数の隣接地所有者が共有するケースも多く、各所有者間の調整が欠かせません。たとえば、土地を取得しても道路部分の共有持分を持たない場合、新たに建築確認を申請すると道路に接していないと見なされ、隣接者全員の同意(建築基準法第43条ただし書き)が求められるなど再建築時に大きな制約が生じます。近年は、これまで道路持分なしでも問題にならなかった土地でも所有者が道路持分を取得するのが標準とされるようになってきています。
位置指定道路上の通行権も問題になります。最高裁判例によれば、歩行や自転車での通行は所有者が全面禁止できないとされます。
一方で、自動車の通行については状況次第で制限が認められており、東京地裁も4m幅未満で袋路状の道路では自動車乗り入れを制限できると判示しました。
共有私道の扱いでは、共有関係を解消する共有物分割請求が争われることがあります。東京地裁令和2年判決(2020年)では、「共有者全員が道路として利用できる」という設立趣旨から、申請者単独所有を認める分割請求を却下しました。
逆に昭和4年判決(1992年)は、一般通行権はあくまで公法的利益で私法の通行権を生じさせないとして、分割請求を認めています。
②建築確認・行政手続きの誤認・不備
位置指定道路をめぐる行政手続きでは、認識のずれや手続きの不備で後々トラブルになる例があります。例えば、昔に道路として指定されながら実際には既に道路が壊されていた土地をめぐり、隣地がその指定道路を前提に建築確認を取得してしまった事案があります。東京高裁は、この土地では道路が1971年に撤去されその必要性も消滅していたため、法的に道路に当たらず、位置指定道路の取消し申請を受理して処分を行うべきであり、関係者の同意は不要と判断しました。
結果として、行政庁が承認していた建築確認は前提が失われたことになり得るのです。同裁判例では「道路が壊されて道路指定の必要性が消滅している場合、その地は建基法上の道路に該当せず、取消し申請があれば行政に裁量余地なく指定取消をすべき」と明示されています。
このように、建築確認申請時に位置指定道路の有無を誤認すると、後日取消し請求や建築許可取り消しといったトラブルに発展しやすいと言えます。
③道路管理義務・修繕費負担のトラブル
位置指定道路は私道扱いのため、維持管理責任はすべて所有者にあります。
国・自治体が補修することはなく、ひび割れや陥没など道路補修の費用は位置指定道路の所有者が負担しなければなりません。
多くの場合、道路を利用する隣接者間で道路部分を共有する形態となっており、補修費用は共有持分に応じて折半するのが一般的です。
たとえば私設の水道管が位置指定道路下で破損した場合も、その補修費用は道路の所有者の負担となります。
このため、共有者の一部が管理費や固定資産税を滞納すると、他の所有者が追加負担を迫られて紛争になる例が少なくありません。補修費用を請求された場合は、「どの部分にどの工事が必要か」「総額はいくらで、誰がどう負担するのか」を事前に明確に確認する必要があります。
④再建築・規制変更のリスク
既存の位置指定道路の条件が変わると、再建築時に思わぬ問題が発覚します。例えば、建築基準法では道路幅が4m以上であることが原則とされており、幅員不足のままでは再建築不可と判断される場合があります。実際、ある事案では道路幅が4m未満であることを理由に再建築できないと判断され、所有者が指定取消しを求めて行政を動かした例があります。また、令和2年の法改正以降は、原則6m道路に対して中心線から2mの後退(セットバック)が必要とされる地域も増え、従来の4m道路では新規確認が下りにくくなりました。旗竿地など敷地が道路に接する部分が2m未満の場合、建築できないリスクがあります。対策としては、前面道路を幅4m以上に拡張するため隣地所有者の同意を得る、同意取得が難しければ43条第2項2号(旧43条但書)による例外規定を検討する、あるいは道路部分を分筆して公衆用道路として再登記するなどが挙げられます。
専門家の指摘によれば、4m未満の袋路状道路でも正式に位置指定を取得すれば再建築が可能になる場合もありますが、幅員4m以上の要件を満たすためのセットバックや関係者合意が障害になりやすい点に注意が必要です。
⑤判例・行政指導事例
・最高裁昭和47年7月25日判決(最三小判昭和47・7・25民集26巻6号1236頁): 位置指定道路の取消しに関して、「取消処分により敷地が建築基準法第43条違反となる場合には、その取消しは違法」と判示し、また処分には所有者の同意が必要とされる趣旨も示されました
・最高裁平成9年12月18日・平成12年1月27日判決: 42条1項5号道路上で障害物があった場合の妨害排除請求について、「自動車通行のために緊急性・必要性がある者だけが妨害排除を請求できる」とし、歩行・自転車通行への制限は認めませんでした
・東京地裁平成23年6月29日判決: 位置指定道路は私道ながら一般公衆通行を許容する性質があるとして、所有者による「歩行・自転車通行の全面禁止」は無効としました。
ただし本件で道路幅約4mの袋路状道路を分析し、車両乗り入れは隣接地利用者の利便を著しく損なう場合があるとして制限可能と判断しています。
・東京地裁平成4年2月28日判決: 位置指定道路として共有されている私道について、共有者の一人が単独所有とする分割請求をしました。裁判所は「一般通行利益は公法的利益であって私法上の通行権を生じさせるものではなく、道路が私道である以上、共有関係の変動は所有者の自由」として、分割請求を認めました。
・東京地裁令和2年7月7日判決: 対照的に、共有者全員による通路利用を前提に土地分譲された事案で、当該用途を害する分割は認められないとして、位置指定道路部分の単独所有化を求める分割請求を却下しました。
・東京高裁平成28年11月30日判決: 昭和26年に指定された位置指定道路が後に撤去された事案で、隣地所有者はその道路を前提に建築確認を取得していました。高裁は「道路が壊され指定の必要性が消滅していれば、法42条上の道路には該当せず、当該指定は取消されるべきであり、所有者承諾は不要」と判断し、行政庁に取消処分を義務付けました。
以上のように、位置指定道路制度に関しては、共有関係・通行権の設定不足、行政認定の誤り、管理費負担や修繕問題、再建築時の法規適合性など多岐にわたる課題とトラブルが指摘されています。裁判例や専門家報告では、取引や建築に際して道路の実態と法的地位を慎重に確認することが重要とされています。
参考資料: 建築基準法第42条1項5号(位置指定道路)、同43条、判例解説、行政庁ガイドライン、建築士・司法書士等の助言・事例報告
位置指定道路は見た目は公道のようでも私道であり、所有者が個人・企業である点に注意が必要です。複数の隣接地所有者が共有するケースも多く、各所有者間の調整が欠かせません。たとえば、土地を取得しても道路部分の共有持分を持たない場合、新たに建築確認を申請すると道路に接していないと見なされ、隣接者全員の同意(建築基準法第43条ただし書き)が求められるなど再建築時に大きな制約が生じます。近年は、これまで道路持分なしでも問題にならなかった土地でも所有者が道路持分を取得するのが標準とされるようになってきています。
位置指定道路上の通行権も問題になります。最高裁判例によれば、歩行や自転車での通行は所有者が全面禁止できないとされます。
一方で、自動車の通行については状況次第で制限が認められており、東京地裁も4m幅未満で袋路状の道路では自動車乗り入れを制限できると判示しました。
共有私道の扱いでは、共有関係を解消する共有物分割請求が争われることがあります。東京地裁令和2年判決(2020年)では、「共有者全員が道路として利用できる」という設立趣旨から、申請者単独所有を認める分割請求を却下しました。
逆に昭和4年判決(1992年)は、一般通行権はあくまで公法的利益で私法の通行権を生じさせないとして、分割請求を認めています。
②建築確認・行政手続きの誤認・不備
位置指定道路をめぐる行政手続きでは、認識のずれや手続きの不備で後々トラブルになる例があります。例えば、昔に道路として指定されながら実際には既に道路が壊されていた土地をめぐり、隣地がその指定道路を前提に建築確認を取得してしまった事案があります。東京高裁は、この土地では道路が1971年に撤去されその必要性も消滅していたため、法的に道路に当たらず、位置指定道路の取消し申請を受理して処分を行うべきであり、関係者の同意は不要と判断しました。
結果として、行政庁が承認していた建築確認は前提が失われたことになり得るのです。同裁判例では「道路が壊されて道路指定の必要性が消滅している場合、その地は建基法上の道路に該当せず、取消し申請があれば行政に裁量余地なく指定取消をすべき」と明示されています。
このように、建築確認申請時に位置指定道路の有無を誤認すると、後日取消し請求や建築許可取り消しといったトラブルに発展しやすいと言えます。
③道路管理義務・修繕費負担のトラブル
位置指定道路は私道扱いのため、維持管理責任はすべて所有者にあります。
国・自治体が補修することはなく、ひび割れや陥没など道路補修の費用は位置指定道路の所有者が負担しなければなりません。
多くの場合、道路を利用する隣接者間で道路部分を共有する形態となっており、補修費用は共有持分に応じて折半するのが一般的です。
たとえば私設の水道管が位置指定道路下で破損した場合も、その補修費用は道路の所有者の負担となります。
このため、共有者の一部が管理費や固定資産税を滞納すると、他の所有者が追加負担を迫られて紛争になる例が少なくありません。補修費用を請求された場合は、「どの部分にどの工事が必要か」「総額はいくらで、誰がどう負担するのか」を事前に明確に確認する必要があります。
④再建築・規制変更のリスク
既存の位置指定道路の条件が変わると、再建築時に思わぬ問題が発覚します。例えば、建築基準法では道路幅が4m以上であることが原則とされており、幅員不足のままでは再建築不可と判断される場合があります。実際、ある事案では道路幅が4m未満であることを理由に再建築できないと判断され、所有者が指定取消しを求めて行政を動かした例があります。また、令和2年の法改正以降は、原則6m道路に対して中心線から2mの後退(セットバック)が必要とされる地域も増え、従来の4m道路では新規確認が下りにくくなりました。旗竿地など敷地が道路に接する部分が2m未満の場合、建築できないリスクがあります。対策としては、前面道路を幅4m以上に拡張するため隣地所有者の同意を得る、同意取得が難しければ43条第2項2号(旧43条但書)による例外規定を検討する、あるいは道路部分を分筆して公衆用道路として再登記するなどが挙げられます。
専門家の指摘によれば、4m未満の袋路状道路でも正式に位置指定を取得すれば再建築が可能になる場合もありますが、幅員4m以上の要件を満たすためのセットバックや関係者合意が障害になりやすい点に注意が必要です。
⑤判例・行政指導事例
・最高裁昭和47年7月25日判決(最三小判昭和47・7・25民集26巻6号1236頁): 位置指定道路の取消しに関して、「取消処分により敷地が建築基準法第43条違反となる場合には、その取消しは違法」と判示し、また処分には所有者の同意が必要とされる趣旨も示されました
・最高裁平成9年12月18日・平成12年1月27日判決: 42条1項5号道路上で障害物があった場合の妨害排除請求について、「自動車通行のために緊急性・必要性がある者だけが妨害排除を請求できる」とし、歩行・自転車通行への制限は認めませんでした
・東京地裁平成23年6月29日判決: 位置指定道路は私道ながら一般公衆通行を許容する性質があるとして、所有者による「歩行・自転車通行の全面禁止」は無効としました。
ただし本件で道路幅約4mの袋路状道路を分析し、車両乗り入れは隣接地利用者の利便を著しく損なう場合があるとして制限可能と判断しています。
・東京地裁平成4年2月28日判決: 位置指定道路として共有されている私道について、共有者の一人が単独所有とする分割請求をしました。裁判所は「一般通行利益は公法的利益であって私法上の通行権を生じさせるものではなく、道路が私道である以上、共有関係の変動は所有者の自由」として、分割請求を認めました。
・東京地裁令和2年7月7日判決: 対照的に、共有者全員による通路利用を前提に土地分譲された事案で、当該用途を害する分割は認められないとして、位置指定道路部分の単独所有化を求める分割請求を却下しました。
・東京高裁平成28年11月30日判決: 昭和26年に指定された位置指定道路が後に撤去された事案で、隣地所有者はその道路を前提に建築確認を取得していました。高裁は「道路が壊され指定の必要性が消滅していれば、法42条上の道路には該当せず、当該指定は取消されるべきであり、所有者承諾は不要」と判断し、行政庁に取消処分を義務付けました。
以上のように、位置指定道路制度に関しては、共有関係・通行権の設定不足、行政認定の誤り、管理費負担や修繕問題、再建築時の法規適合性など多岐にわたる課題とトラブルが指摘されています。裁判例や専門家報告では、取引や建築に際して道路の実態と法的地位を慎重に確認することが重要とされています。
参考資料: 建築基準法第42条1項5号(位置指定道路)、同43条、判例解説、行政庁ガイドライン、建築士・司法書士等の助言・事例報告
3. 申請手続きの流れ

3-1. 申請に必要な書類と手数料

位置指定道路の申請を行うには、建築基準法第42条1項5号に基づき、市区町村や都道府県など所轄の建築主事がいる行政庁へ申請を行う必要があります。申請時には、以下のような必要書類や図面類が求められます。
【主な必要書類】
・位置指定道路指定申請書(様式有)
自治体が指定する申請用紙に沿って記入します。
・土地の登記事項証明書(全部事項証明)
道路に該当する土地の所有者を確認するために必要です。共有の場合は全員分が必要。
・公図および地積測量図
敷地の正確な位置・形状を示すもの。
・道路位置図(案内図)
周辺状況や接続先の公道との関係を明記します。
・平面図・縦断図・横断図
道路の勾配、幅員、排水勾配などを記載。道路設計基準に合致している必要があります。
・排水計画図・雨水・汚水処理図
側溝や排水の処理方法が明記された図面。
・構造図(舗装、側溝等の詳細)
舗装厚、縁石、側溝などの構造的仕様を示します。
・境界確認書・同意書
隣接地所有者の承諾が必要なケースでは、その署名・捺印付きの書類。
・設計者資格証の写し(建築士・土木施工管理技士等)
道路設計を担当した者の資格証明。
【主な必要書類】
・位置指定道路指定申請書(様式有)
自治体が指定する申請用紙に沿って記入します。
・土地の登記事項証明書(全部事項証明)
道路に該当する土地の所有者を確認するために必要です。共有の場合は全員分が必要。
・公図および地積測量図
敷地の正確な位置・形状を示すもの。
・道路位置図(案内図)
周辺状況や接続先の公道との関係を明記します。
・平面図・縦断図・横断図
道路の勾配、幅員、排水勾配などを記載。道路設計基準に合致している必要があります。
・排水計画図・雨水・汚水処理図
側溝や排水の処理方法が明記された図面。
・構造図(舗装、側溝等の詳細)
舗装厚、縁石、側溝などの構造的仕様を示します。
・境界確認書・同意書
隣接地所有者の承諾が必要なケースでは、その署名・捺印付きの書類。
・設計者資格証の写し(建築士・土木施工管理技士等)
道路設計を担当した者の資格証明。
3-2. 申請から指定までのステップ

位置指定道路の指定を受けるには、建築基準法第42条第1項第5号に基づく厳密な手続きが必要です。以下は、一般的な申請から指定までの流れをステップ形式で整理したものです。
【ステップ①:事前相談】
まず、申請予定の自治体の建築指導課や開発指導課に事前相談を行います。ここで以下を確認します:
・対象地が位置指定道路として認められるか
・道路幅や構造基準の可否
・提出書類の詳細や様式
※ この段階で設計や計画に対してアドバイスを受けておくと、後の修正を減らせます。
【ステップ②:書類・図面の準備】
前項(3-1)で挙げた書類や図面を建築士や設計士、測量士と協力しながら準備します。提出資料にミスや不備があると差し戻されるため、専門家の関与が重要です。
【ステップ③:申請書の提出】
必要書類を整えたら、管轄行政庁に申請書を正式提出します。
・申請書受理後、行政側が形式審査を行い、問題がなければ技術審査へと進みます。
・審査期間は通常1~2か月程度ですが、内容や自治体によって異なることがあります。
【ステップ④:現地調査・ヒアリング】
行政担当者が現地を確認し、道路の幅員、勾配、排水計画、隣接地との関係などを調査します。
・必要に応じて追加資料や補足説明を求められる場合があります。
・この段階でトラブルや未解決の境界問題が発覚することもあるため注意が必要です。
【ステップ⑤:位置指定通知の交付】
すべての審査に通過すると、「位置指定道路指定通知書」が交付され、正式に位置指定道路として認可されます。
・通知を受けた日からその道路は法42条1項5号の道路として扱われます。
・以後、その道路に面した土地で建築確認申請が可能になります。
【補足】
指定後も、維持管理義務は所有者に残る点に注意。
指定取り消しとなる事例(例:構造物の違法設置や放置)もあるため、継続的な管理が求められます。
【ステップ①:事前相談】
まず、申請予定の自治体の建築指導課や開発指導課に事前相談を行います。ここで以下を確認します:
・対象地が位置指定道路として認められるか
・道路幅や構造基準の可否
・提出書類の詳細や様式
※ この段階で設計や計画に対してアドバイスを受けておくと、後の修正を減らせます。
【ステップ②:書類・図面の準備】
前項(3-1)で挙げた書類や図面を建築士や設計士、測量士と協力しながら準備します。提出資料にミスや不備があると差し戻されるため、専門家の関与が重要です。
【ステップ③:申請書の提出】
必要書類を整えたら、管轄行政庁に申請書を正式提出します。
・申請書受理後、行政側が形式審査を行い、問題がなければ技術審査へと進みます。
・審査期間は通常1~2か月程度ですが、内容や自治体によって異なることがあります。
【ステップ④:現地調査・ヒアリング】
行政担当者が現地を確認し、道路の幅員、勾配、排水計画、隣接地との関係などを調査します。
・必要に応じて追加資料や補足説明を求められる場合があります。
・この段階でトラブルや未解決の境界問題が発覚することもあるため注意が必要です。
【ステップ⑤:位置指定通知の交付】
すべての審査に通過すると、「位置指定道路指定通知書」が交付され、正式に位置指定道路として認可されます。
・通知を受けた日からその道路は法42条1項5号の道路として扱われます。
・以後、その道路に面した土地で建築確認申請が可能になります。
【補足】
指定後も、維持管理義務は所有者に残る点に注意。
指定取り消しとなる事例(例:構造物の違法設置や放置)もあるため、継続的な管理が求められます。
4. 注意点とトラブル防止策

4-1. 通行権や管理責任の明確化

位置指定道路や私道においては、通行権の所在や管理責任の範囲が曖昧なままだと、後々トラブルの原因になりやすいため、事前に明確にしておくことが非常に重要です。
■ 通行権の明確化
位置指定道路であっても私道である以上、所有者の同意なく第三者が自由に通行できるわけではありません。そのため、以下のような取り決めが必要です:
・【通行承諾書】… 通行を必要とする隣地所有者と位置指定道路の所有者間で締結
・【地役権の設定】… 登記で通行権を法的に担保することで、将来的な売買・相続にも影響しにくくなります
・【持分共有の確認】… 道路を複数人で共有する場合、全員の合意を得る体制が必要です
※ 登記されていない「口約束の通行」では、法的効力が弱くトラブルの元になります。
■ 管理責任の明確化
位置指定道路は、原則として所有者が管理責任を負うことになります。管理とは以下のような行為を含みます:
・道路の補修・舗装
・排水機能の維持(側溝の清掃など)
・草木の伐採、通行の安全確保
所有者が複数いる共有私道では、「管理規約」や「覚書」などを文書で取り交わしておくことが望ましいです。これにより、費用負担や緊急時の対応について揉めるリスクを減らせます。
■ 明確化しない場合のリスク
・建築確認申請が通らない可能性がある
・建物完成後に通行トラブルが発生し、住めなくなるリスク
・道路修繕にかかる費用を一部負担してもらえず、自己負担が増す
通行権と管理責任は、売買や相続時にも影響する重要事項です。必ず契約書・図面・登記簿で根拠を残しておくようにしましょう。
■ 通行権の明確化
位置指定道路であっても私道である以上、所有者の同意なく第三者が自由に通行できるわけではありません。そのため、以下のような取り決めが必要です:
・【通行承諾書】… 通行を必要とする隣地所有者と位置指定道路の所有者間で締結
・【地役権の設定】… 登記で通行権を法的に担保することで、将来的な売買・相続にも影響しにくくなります
・【持分共有の確認】… 道路を複数人で共有する場合、全員の合意を得る体制が必要です
※ 登記されていない「口約束の通行」では、法的効力が弱くトラブルの元になります。
■ 管理責任の明確化
位置指定道路は、原則として所有者が管理責任を負うことになります。管理とは以下のような行為を含みます:
・道路の補修・舗装
・排水機能の維持(側溝の清掃など)
・草木の伐採、通行の安全確保
所有者が複数いる共有私道では、「管理規約」や「覚書」などを文書で取り交わしておくことが望ましいです。これにより、費用負担や緊急時の対応について揉めるリスクを減らせます。
■ 明確化しない場合のリスク
・建築確認申請が通らない可能性がある
・建物完成後に通行トラブルが発生し、住めなくなるリスク
・道路修繕にかかる費用を一部負担してもらえず、自己負担が増す
通行権と管理責任は、売買や相続時にも影響する重要事項です。必ず契約書・図面・登記簿で根拠を残しておくようにしましょう。
4-2. 将来的な維持管理計画の策定
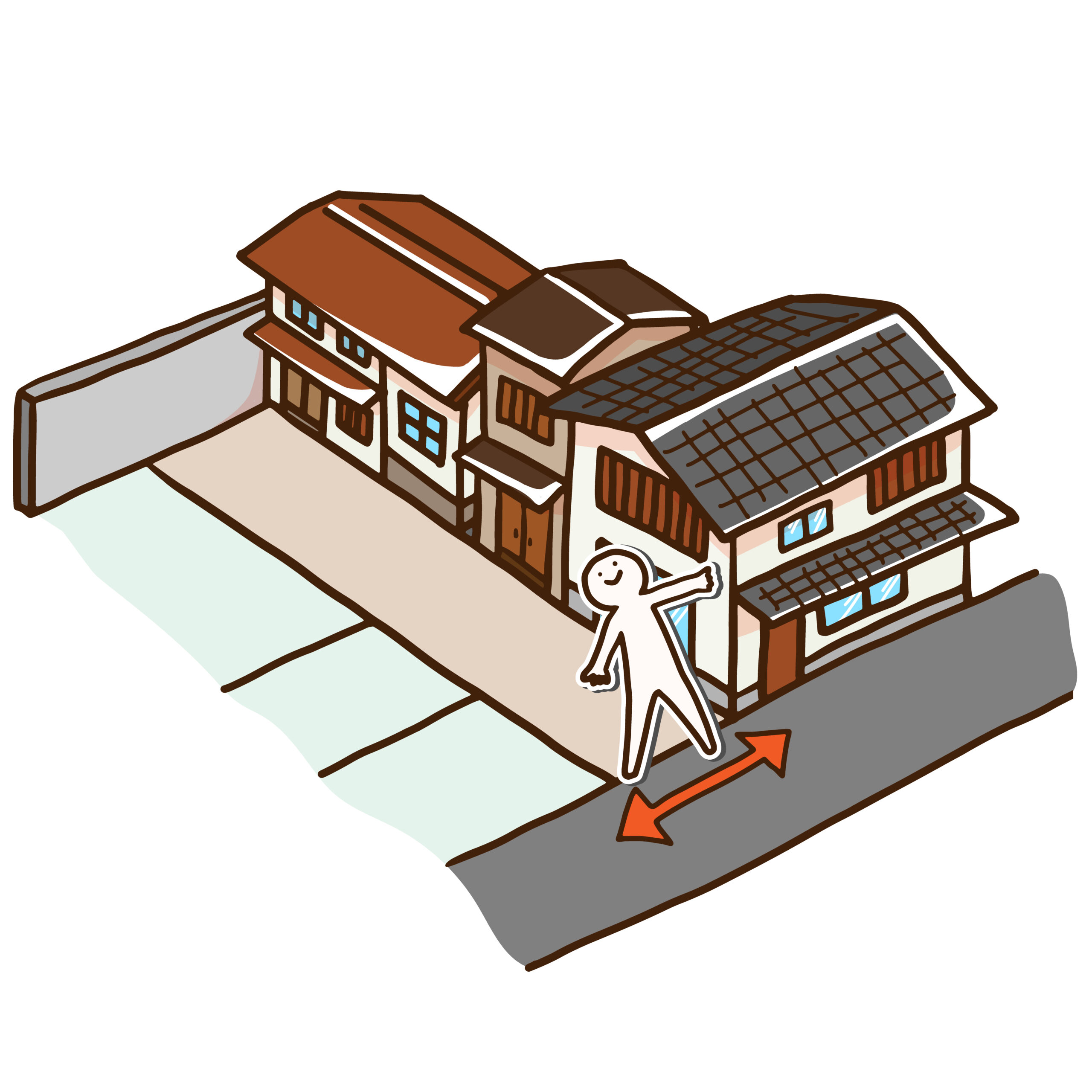
位置指定道路や私道を円滑に運用し続けるためには、長期的な維持管理計画の策定が不可欠です。道路の損傷や排水トラブル、老朽化は避けられない問題であり、予防と計画的な対応が将来のトラブル回避につながります。
■ なぜ維持管理計画が必要か?
・年数経過による舗装劣化・雨水排水不良など、修繕が必要になる場面は必ず訪れる
・所有者が高齢化や相続によって変化すると、責任や負担の所在が不明確になりやすい
・修繕や管理費用をその都度話し合うのは非効率で、トラブルの原因になる
■ 計画に含めるべき主な要素
1.管理責任者の明確化
個人または共有者の中で代表を決め、責任の所在を明確にしておく。
2.定期点検のスケジュール
例:年1回の目視点検や、5年ごとの専門業者による診断など。
3.維持修繕の基準と内容
小さなひび割れの補修、排水溝の清掃、舗装の再施工など対応範囲を明記。
4.費用負担のルール
持分に応じた負担割合、または均等負担など。口頭ではなく文書化する。
5.トラブル時の対応手順
住民同士の合意形成フローや、第三者(町内会・弁護士等)への相談窓口も検討。
■ 管理組合や協定の活用
位置指定道路を含む分譲地や共有私道では、住民組織(管理組合)を設けておくと、合意形成や実行力が高まります。協定書を公正証書化することで、将来的な法的トラブルにも備えられます。
長期的な維持管理計画は、資産価値を保つだけでなく、住民の安心にもつながる重要なインフラマネジメントです。今のうちから計画を立てておくことをおすすめします。
以下に、位置指定道路・私道の維持管理に関する協定書の文例を記載します。実際の運用に際しては、法的効力を持たせるために公正証書化や専門家(司法書士・行政書士・弁護士など)の確認を推奨します。↓↓↓↓
私道(位置指定道路)維持管理協定書(文例)
第1条(目的)
本協定は、〇〇市〇〇町所在の私道(以下「本道路」という)の維持管理について、所有者間の責任と費用負担を明確にし、道路の適正な管理と円滑な通行の確保を図ることを目的とする。
第2条(対象道路)
本協定の対象は、地番〇〇番〇(延長〇m、幅員〇m)に位置する私道とする。
第3条(管理責任)
本道路の管理責任者は、〇〇(氏名または代表者名)とする。
管理責任者は、定期点検・簡易修繕・清掃などの維持業務を取りまとめるものとする。
第4条(点検・修繕)
毎年〇月に簡易点検を行い、修繕の要否を検討する。
修繕が必要な場合は、管理責任者の報告に基づき所有者間で協議し、内容と実施時期を決定する。
第5条(費用負担)
維持管理に要する費用は、各所有者の土地持分比率に応じて負担する。
費用は、修繕実施前に見積書に基づき算出し、所有者に通知の上で徴収する。
第6条(通行と使用)
所有者は本道路を通行目的の範囲内で自由に使用できる。
車両の通行・駐車に関しては、所有者間で定めたルールに従うこと。
第7条(所有者変更時の承継)
本協定の内容は、所有者が変更された場合でも継続して効力を持ち、新所有者に承継されるものとする。
第8条(協議事項)
本協定に定めのない事項、または不明確な事項が発生した場合は、所有者間で協議し解決を図るものとする。
以上の内容を確認し、下記の通り署名・押印する。
所有者氏名 住所 押印
〇〇〇〇 〇〇市〇〇町〇〇番地 印
〇〇〇〇 〇〇市〇〇町〇〇番地 印
... ... ...
作成日:令和〇年〇月〇日
■ なぜ維持管理計画が必要か?
・年数経過による舗装劣化・雨水排水不良など、修繕が必要になる場面は必ず訪れる
・所有者が高齢化や相続によって変化すると、責任や負担の所在が不明確になりやすい
・修繕や管理費用をその都度話し合うのは非効率で、トラブルの原因になる
■ 計画に含めるべき主な要素
1.管理責任者の明確化
個人または共有者の中で代表を決め、責任の所在を明確にしておく。
2.定期点検のスケジュール
例:年1回の目視点検や、5年ごとの専門業者による診断など。
3.維持修繕の基準と内容
小さなひび割れの補修、排水溝の清掃、舗装の再施工など対応範囲を明記。
4.費用負担のルール
持分に応じた負担割合、または均等負担など。口頭ではなく文書化する。
5.トラブル時の対応手順
住民同士の合意形成フローや、第三者(町内会・弁護士等)への相談窓口も検討。
■ 管理組合や協定の活用
位置指定道路を含む分譲地や共有私道では、住民組織(管理組合)を設けておくと、合意形成や実行力が高まります。協定書を公正証書化することで、将来的な法的トラブルにも備えられます。
長期的な維持管理計画は、資産価値を保つだけでなく、住民の安心にもつながる重要なインフラマネジメントです。今のうちから計画を立てておくことをおすすめします。
以下に、位置指定道路・私道の維持管理に関する協定書の文例を記載します。実際の運用に際しては、法的効力を持たせるために公正証書化や専門家(司法書士・行政書士・弁護士など)の確認を推奨します。↓↓↓↓
私道(位置指定道路)維持管理協定書(文例)
第1条(目的)
本協定は、〇〇市〇〇町所在の私道(以下「本道路」という)の維持管理について、所有者間の責任と費用負担を明確にし、道路の適正な管理と円滑な通行の確保を図ることを目的とする。
第2条(対象道路)
本協定の対象は、地番〇〇番〇(延長〇m、幅員〇m)に位置する私道とする。
第3条(管理責任)
本道路の管理責任者は、〇〇(氏名または代表者名)とする。
管理責任者は、定期点検・簡易修繕・清掃などの維持業務を取りまとめるものとする。
第4条(点検・修繕)
毎年〇月に簡易点検を行い、修繕の要否を検討する。
修繕が必要な場合は、管理責任者の報告に基づき所有者間で協議し、内容と実施時期を決定する。
第5条(費用負担)
維持管理に要する費用は、各所有者の土地持分比率に応じて負担する。
費用は、修繕実施前に見積書に基づき算出し、所有者に通知の上で徴収する。
第6条(通行と使用)
所有者は本道路を通行目的の範囲内で自由に使用できる。
車両の通行・駐車に関しては、所有者間で定めたルールに従うこと。
第7条(所有者変更時の承継)
本協定の内容は、所有者が変更された場合でも継続して効力を持ち、新所有者に承継されるものとする。
第8条(協議事項)
本協定に定めのない事項、または不明確な事項が発生した場合は、所有者間で協議し解決を図るものとする。
以上の内容を確認し、下記の通り署名・押印する。
所有者氏名 住所 押印
〇〇〇〇 〇〇市〇〇町〇〇番地 印
〇〇〇〇 〇〇市〇〇町〇〇番地 印
... ... ...
作成日:令和〇年〇月〇日
5. まとめとアドバイス

5-1. 位置指定道路の活用に向けて

位置指定道路は、建築基準法上の「道路」として扱われるため、沿道に建物を新築・増改築できるという点で大きな活用価値があります。特に相続や空き家の活用、土地分筆・売却などの場面で、建築可能な土地として市場価値を高める要素となります。
また、適切な管理と申請が行われていれば、戸建て住宅の開発やアパート建設などの不動産活用も現実的になります。法的整備をしっかり行うことで、私道にある不動産の活用幅が大きく広がるのです。
ただし、活用にあたっては通行権の確保や維持管理協定の締結、関係者間の合意形成が重要です。将来的なトラブルを防ぐためにも、専門家のサポートを受けながら準備を進めることが望まれます。
また、適切な管理と申請が行われていれば、戸建て住宅の開発やアパート建設などの不動産活用も現実的になります。法的整備をしっかり行うことで、私道にある不動産の活用幅が大きく広がるのです。
ただし、活用にあたっては通行権の確保や維持管理協定の締結、関係者間の合意形成が重要です。将来的なトラブルを防ぐためにも、専門家のサポートを受けながら準備を進めることが望まれます。
5-2. 今後の課題と制度整備

位置指定道路を円滑に活用していくためには、いくつかの課題と今後の制度整備が必要です。まず、所有者や利用者間の権利関係が複雑であるケースが多く、通行・掘削・維持管理に関する合意形成が容易ではありません。とくに相続などで所有者不明となると、申請や管理が滞る要因となります。
さらに、自治体ごとの対応や指導基準が異なるため、利用者にとっては分かりづらく、申請プロセスが不透明なことも問題です。こうした背景を踏まえ、国や自治体によるガイドラインの標準化やオンライン申請の整備など、制度の簡素化と透明性の向上が求められています。
今後は、地域住民・行政・専門家が連携し、位置指定道路の円滑な利活用を図るための仕組みづくりが一層重要になるでしょう。
さらに、自治体ごとの対応や指導基準が異なるため、利用者にとっては分かりづらく、申請プロセスが不透明なことも問題です。こうした背景を踏まえ、国や自治体によるガイドラインの標準化やオンライン申請の整備など、制度の簡素化と透明性の向上が求められています。
今後は、地域住民・行政・専門家が連携し、位置指定道路の円滑な利活用を図るための仕組みづくりが一層重要になるでしょう。
5-3. 専門家への相談の重要性

位置指定道路の申請や維持管理においては、法的・技術的な知識が必要不可欠です。とくに私道が絡むケースでは、権利関係が複雑になりがちで、法的リスクやトラブル回避のために専門家の助言が非常に重要です。
具体的には、土地家屋調査士、司法書士、行政書士、建築士、不動産コンサルタントなどの専門家が関与することで、申請書類の正確な作成、境界の確定、管理協定の作成・締結などがスムーズに進みます。
また、専門家は自治体ごとの条例や運用の違いにも精通しており、地域特有の課題にも的確に対応できます。費用はかかるものの、後々のトラブルを防ぎ、スムーズな運用を実現するうえで、専門家への相談はコストではなく“安心”への投資といえるでしょう。
■ 位置指定道路・私道管理に関する相談先の例
専門家 主な役割・相談内容
土地家屋調査士 境界の確定、分筆や測量図の作成、筆界確認の支援
行政書士 位置指定道路申請書類の作成支援、各種行政手続きの代行
司法書士 所有権・通行地役権の登記、権利関係の調整
建築士 道路幅員や安全性等の設計、建築基準法適合のアドバイス
不動産コンサルタント/宅建士 活用方法やリスクの評価、売買時のアドバイス
■ 専門家相談前に確認すべきチェックリスト(5項目)
1.対象道路の所有者が明確になっているか?
→ 複数名義、共有名義の場合は事前に確認が必要です。
2.道路幅員・形状が建築基準法に適合しているか?
→ 最低4m必要とされるケースが多いため、現地測量を確認。
3.既に位置指定道路として認定されているか?
→ 市区町村の建築課・道路課などに事前確認を。
4.近隣住民との通行や維持管理についての合意はあるか?
→ 将来のトラブルを避けるため、協定書の整備を検討。
5.今後の再建築や売却予定はあるか?
→ 利活用の目的によって、申請や契約内容が変わるため要整理。
具体的には、土地家屋調査士、司法書士、行政書士、建築士、不動産コンサルタントなどの専門家が関与することで、申請書類の正確な作成、境界の確定、管理協定の作成・締結などがスムーズに進みます。
また、専門家は自治体ごとの条例や運用の違いにも精通しており、地域特有の課題にも的確に対応できます。費用はかかるものの、後々のトラブルを防ぎ、スムーズな運用を実現するうえで、専門家への相談はコストではなく“安心”への投資といえるでしょう。
■ 位置指定道路・私道管理に関する相談先の例
専門家 主な役割・相談内容
土地家屋調査士 境界の確定、分筆や測量図の作成、筆界確認の支援
行政書士 位置指定道路申請書類の作成支援、各種行政手続きの代行
司法書士 所有権・通行地役権の登記、権利関係の調整
建築士 道路幅員や安全性等の設計、建築基準法適合のアドバイス
不動産コンサルタント/宅建士 活用方法やリスクの評価、売買時のアドバイス
■ 専門家相談前に確認すべきチェックリスト(5項目)
1.対象道路の所有者が明確になっているか?
→ 複数名義、共有名義の場合は事前に確認が必要です。
2.道路幅員・形状が建築基準法に適合しているか?
→ 最低4m必要とされるケースが多いため、現地測量を確認。
3.既に位置指定道路として認定されているか?
→ 市区町村の建築課・道路課などに事前確認を。
4.近隣住民との通行や維持管理についての合意はあるか?
→ 将来のトラブルを避けるため、協定書の整備を検討。
5.今後の再建築や売却予定はあるか?
→ 利活用の目的によって、申請や契約内容が変わるため要整理。
