2023年に施行された「改正空き家対策特別措置法」により、空き家問題への対応が強化され、行政には新たな課題が生じています。特に、空き家の発生を未然に防ぐための施策が求められています。このような中、国土交通省が作成した「住まいのエンディングノート」は、住まいの将来について家族で話し合うきっかけを提供し、空き家の発生抑制に寄与するツールとして注目されています。本記事では、改正法の概要、行政が直面する課題、「住まいのエンディングノート」の活用法、そして実際の活用事例について詳しく解説します。

1. 改正空き家対策特別措置法の概要と背景

1-1. 改正法の主なポイントと施行の背景

■ 背景:急増する空き家とその社会的影響
近年、日本全国で居住目的のない空き家が急増しています。総務省の住宅・土地統計調査によると、1998年には約182万戸だった居住目的のない空き家が、2018年には約349万戸と約1.9倍に増加しました。このままの傾向が続けば、2030年には約470万戸に達すると推計されています 。
これらの空き家は、倒壊や衛生問題、景観の悪化など、地域社会に多大な悪影響を及ぼす可能性があります。従来の法律では、既に問題が顕在化した「特定空家」への対応が中心であり、予防的な措置が不十分でした。
■ 改正の目的:早期対応と予防的措置の強化
このような背景を受け、2023年に「空家等対策特別措置法」が改正され、以下の点が強化されました:
・「管理不全空家」の新設:特定空家になる前の段階で、管理が不十分な空き家を「管理不全空家」として指定し、早期に指導・勧告が可能となりました 。
・所有者の責務強化:空き家の所有者に対し、適切な管理の努力義務に加え、国や自治体の施策に協力する努力義務が追加されました 。
・空家等活用促進区域の創設:自治体が指定する区域内で、空き家の活用を促進するための指針を策定し、所有者に対して活用を要請できるようになりました
・緊急代執行制度の創設:特定空家に対して、猶予期間を設けずに速やかに代執行を実施できる制度が導入されました 。
これらの改正により、空き家問題への早期対応と予防的措置が強化され、地域の安全・安心な住環境の維持が期待されています。
近年、日本全国で居住目的のない空き家が急増しています。総務省の住宅・土地統計調査によると、1998年には約182万戸だった居住目的のない空き家が、2018年には約349万戸と約1.9倍に増加しました。このままの傾向が続けば、2030年には約470万戸に達すると推計されています 。
これらの空き家は、倒壊や衛生問題、景観の悪化など、地域社会に多大な悪影響を及ぼす可能性があります。従来の法律では、既に問題が顕在化した「特定空家」への対応が中心であり、予防的な措置が不十分でした。
■ 改正の目的:早期対応と予防的措置の強化
このような背景を受け、2023年に「空家等対策特別措置法」が改正され、以下の点が強化されました:
・「管理不全空家」の新設:特定空家になる前の段階で、管理が不十分な空き家を「管理不全空家」として指定し、早期に指導・勧告が可能となりました 。
・所有者の責務強化:空き家の所有者に対し、適切な管理の努力義務に加え、国や自治体の施策に協力する努力義務が追加されました 。
・空家等活用促進区域の創設:自治体が指定する区域内で、空き家の活用を促進するための指針を策定し、所有者に対して活用を要請できるようになりました
・緊急代執行制度の創設:特定空家に対して、猶予期間を設けずに速やかに代執行を実施できる制度が導入されました 。
これらの改正により、空き家問題への早期対応と予防的措置が強化され、地域の安全・安心な住環境の維持が期待されています。
1-2. 空き家問題が社会にもたらす影響

■ 1. 防災・防犯リスクの増大
適切に管理されていない空き家は、老朽化により倒壊や火災のリスクが高まります。また、不審者の侵入や放火の温床となり、地域の防犯性が低下します。国土交通省の資料によれば、空き家による外部不経済は、防災・防犯、衛生、景観など多岐にわたり、大きな問題とされています。
■ 2. 衛生環境の悪化
放置された空き家は、雑草の繁茂や害虫・害獣の発生源となり、悪臭や衛生問題を引き起こします。これにより、近隣住民の生活環境が悪化し、地域の住みやすさが損なわれます。
■ 3. 景観の悪化と地域イメージの低下
外観が損なわれた空き家は、地域の景観を悪化させ、街全体のイメージダウンにつながります。特に観光地や住宅地では、その影響が顕著であり、街全体の魅力が低下する可能性があります。
■ 4. 地価の下落と経済的損失
空き家が増加することで、周辺の不動産価値が下落し、地域経済に悪影響を及ぼします。実際、日本の不動産市場では、空き家の増加により数千億円規模の損失が発生していると報告されています。
■ 5. 地域コミュニティの衰退
空き家の増加は、人口減少や高齢化を加速させ、地域コミュニティの活力を低下させます。これにより、地域の持続可能性が脅かされ、さらなる人口流出を招く悪循環に陥る可能性があります。
これらの影響を踏まえ、空き家問題への早期対応と予防的措置が求められています。地域社会全体で協力し、空き家の適切な管理と活用を進めることが、持続可能な地域づくりにつながります。
適切に管理されていない空き家は、老朽化により倒壊や火災のリスクが高まります。また、不審者の侵入や放火の温床となり、地域の防犯性が低下します。国土交通省の資料によれば、空き家による外部不経済は、防災・防犯、衛生、景観など多岐にわたり、大きな問題とされています。
■ 2. 衛生環境の悪化
放置された空き家は、雑草の繁茂や害虫・害獣の発生源となり、悪臭や衛生問題を引き起こします。これにより、近隣住民の生活環境が悪化し、地域の住みやすさが損なわれます。
■ 3. 景観の悪化と地域イメージの低下
外観が損なわれた空き家は、地域の景観を悪化させ、街全体のイメージダウンにつながります。特に観光地や住宅地では、その影響が顕著であり、街全体の魅力が低下する可能性があります。
■ 4. 地価の下落と経済的損失
空き家が増加することで、周辺の不動産価値が下落し、地域経済に悪影響を及ぼします。実際、日本の不動産市場では、空き家の増加により数千億円規模の損失が発生していると報告されています。
■ 5. 地域コミュニティの衰退
空き家の増加は、人口減少や高齢化を加速させ、地域コミュニティの活力を低下させます。これにより、地域の持続可能性が脅かされ、さらなる人口流出を招く悪循環に陥る可能性があります。
これらの影響を踏まえ、空き家問題への早期対応と予防的措置が求められています。地域社会全体で協力し、空き家の適切な管理と活用を進めることが、持続可能な地域づくりにつながります。
2. 行政が直面する課題と対応策

2-1. 人員不足と専門知識の欠如

■ 人員不足の現状
多くの自治体では、空き家対策を担当する専門部署が設置されておらず、総務課や税務課の職員が他業務と兼任で対応しているケースが一般的です。このような体制では、空き家問題に十分な時間と労力を割くことが難しく、対応が後手に回る傾向があります。特に小規模自治体では、専任の担当者を配置することが困難であり、慢性的な人手不足が深刻な問題となっています。
■ 専門知識の不足
空き家対策には、建築基準法や相続、税制、不動産取引など多岐にわたる専門知識が求められます。しかし、自治体職員の多くはこれらの分野に精通しておらず、適切な対応が難しい状況です。例えば、空き家の相談窓口においては、46.6%の担当者が「空き家の相談受付・活用マッチングに関する専門知識の不足」を課題として挙げています。
■ 対応策と今後の展望
これらの課題に対応するため、国は「空家等管理活用支援法人」の制度を導入しました。この制度により、自治体は空き家の活用や管理に精通したNPO法人や一般社団法人を指定し、業務をアウトソーシングすることが可能となります。これにより、自治体職員の負担軽減と専門性の確保が期待されています。
また、地域における人材育成も重要です。例えば、三重県南伊勢町では、地域おこし協力隊と連携し、「空き家再生プロデューサー」の育成プログラムを実施しています。これにより、地域内で空き家の利活用を担う人材を育成し、持続可能な対策体制の構築を目指しています。
人員不足と専門知識の欠如は、空き家対策の推進を妨げる大きな要因です。今後は、官民連携や地域人材の育成を通じて、これらの課題を克服し、効果的な空き家対策を実現することが求められます。
多くの自治体では、空き家対策を担当する専門部署が設置されておらず、総務課や税務課の職員が他業務と兼任で対応しているケースが一般的です。このような体制では、空き家問題に十分な時間と労力を割くことが難しく、対応が後手に回る傾向があります。特に小規模自治体では、専任の担当者を配置することが困難であり、慢性的な人手不足が深刻な問題となっています。
■ 専門知識の不足
空き家対策には、建築基準法や相続、税制、不動産取引など多岐にわたる専門知識が求められます。しかし、自治体職員の多くはこれらの分野に精通しておらず、適切な対応が難しい状況です。例えば、空き家の相談窓口においては、46.6%の担当者が「空き家の相談受付・活用マッチングに関する専門知識の不足」を課題として挙げています。
■ 対応策と今後の展望
これらの課題に対応するため、国は「空家等管理活用支援法人」の制度を導入しました。この制度により、自治体は空き家の活用や管理に精通したNPO法人や一般社団法人を指定し、業務をアウトソーシングすることが可能となります。これにより、自治体職員の負担軽減と専門性の確保が期待されています。
また、地域における人材育成も重要です。例えば、三重県南伊勢町では、地域おこし協力隊と連携し、「空き家再生プロデューサー」の育成プログラムを実施しています。これにより、地域内で空き家の利活用を担う人材を育成し、持続可能な対策体制の構築を目指しています。
人員不足と専門知識の欠如は、空き家対策の推進を妨げる大きな要因です。今後は、官民連携や地域人材の育成を通じて、これらの課題を克服し、効果的な空き家対策を実現することが求められます。
2-2. 所有者不明土地への対応の難しさ

■ 所有者特定の困難さ
所有者不明土地とは、登記簿上で所有者が判明しない、または連絡が取れない土地を指します。その主な原因は、相続登記が未了であることや、所有者が多数に分散していることです。例えば、ある事例では、相続人が約242名に上り、そのうち3名が所在不明であったため、交渉や手続きに1年10ヶ月を要したケースもあります。
また、登記情報が古く、所有者が「A外〇名」としか記載されていない場合や、法人が解散しているケースでは、所有者の特定が一層困難となります。
■ 法的・手続き上の制約
所有者不明土地に対しては、現行制度では土地収用法の適用が難しい場合が多く、代執行や管理代行の手続きも煩雑で時間がかかります。また、個人情報保護法の影響で、市町村が所有者情報を取得する手続きが複雑化しており、迅速な対応が難しくなっています。
■ 地域社会への影響
所有者不明土地は、管理が行き届かないため、雑草の繁茂や不法投棄の温床となり、地域の景観や衛生環境を悪化させます。さらに、防災・防犯上のリスクも高まり、地域住民の生活に直接的な影響を及ぼします。これにより、地域の魅力が低下し、人口流出や経済活動の停滞を招く恐れがあります。
これらの課題に対応するため、国や自治体は「所有者不明土地対策計画」の策定や、所有者探索の合理化、情報共有の促進など、さまざまな取り組みを進めています。しかし、実効性のある対策を講じるためには、法制度の見直しや、地域住民との連携強化が不可欠です。
所有者不明土地とは、登記簿上で所有者が判明しない、または連絡が取れない土地を指します。その主な原因は、相続登記が未了であることや、所有者が多数に分散していることです。例えば、ある事例では、相続人が約242名に上り、そのうち3名が所在不明であったため、交渉や手続きに1年10ヶ月を要したケースもあります。
また、登記情報が古く、所有者が「A外〇名」としか記載されていない場合や、法人が解散しているケースでは、所有者の特定が一層困難となります。
■ 法的・手続き上の制約
所有者不明土地に対しては、現行制度では土地収用法の適用が難しい場合が多く、代執行や管理代行の手続きも煩雑で時間がかかります。また、個人情報保護法の影響で、市町村が所有者情報を取得する手続きが複雑化しており、迅速な対応が難しくなっています。
■ 地域社会への影響
所有者不明土地は、管理が行き届かないため、雑草の繁茂や不法投棄の温床となり、地域の景観や衛生環境を悪化させます。さらに、防災・防犯上のリスクも高まり、地域住民の生活に直接的な影響を及ぼします。これにより、地域の魅力が低下し、人口流出や経済活動の停滞を招く恐れがあります。
これらの課題に対応するため、国や自治体は「所有者不明土地対策計画」の策定や、所有者探索の合理化、情報共有の促進など、さまざまな取り組みを進めています。しかし、実効性のある対策を講じるためには、法制度の見直しや、地域住民との連携強化が不可欠です。
3. 「住まいのエンディングノート」の活用法
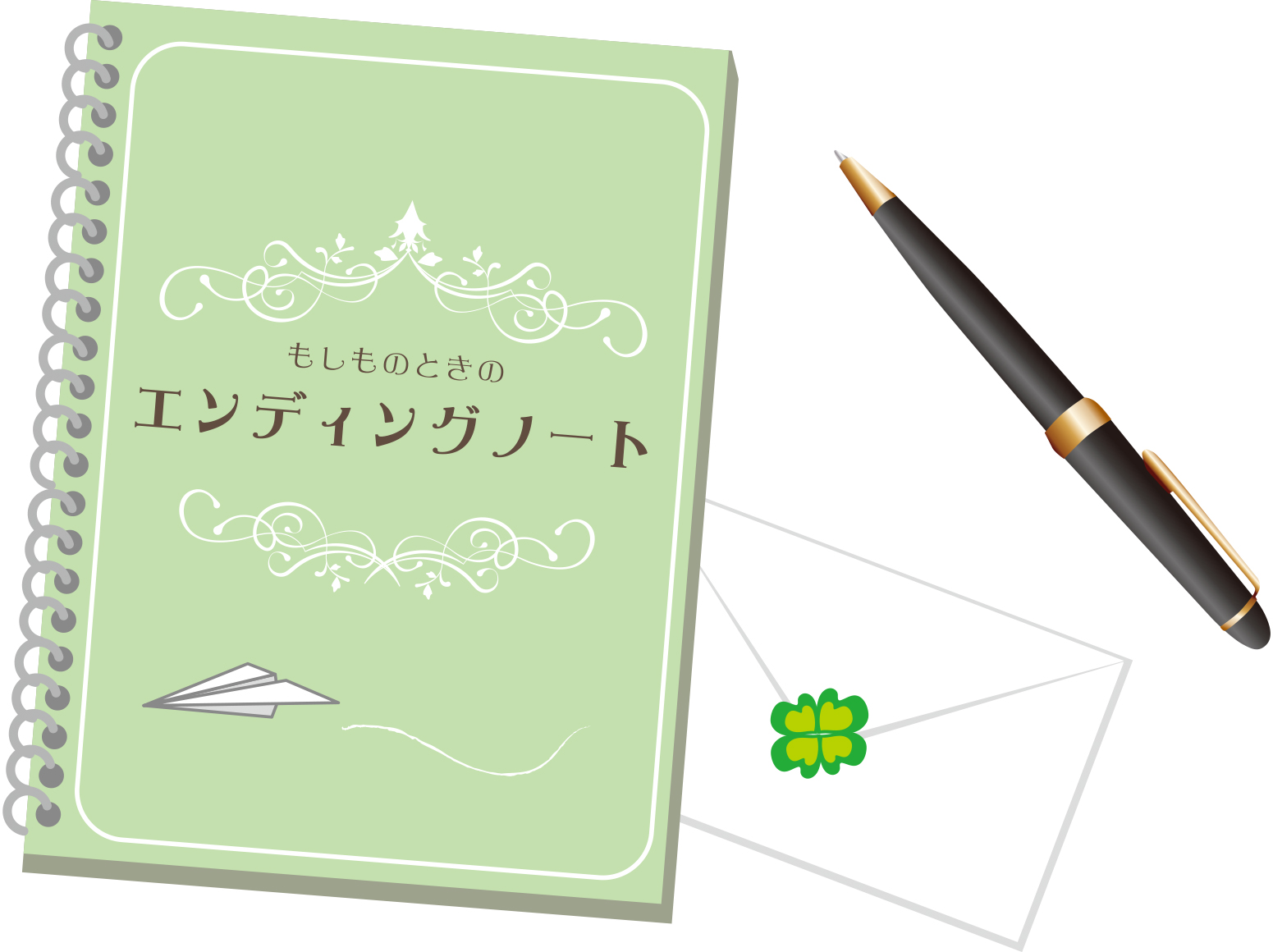
3-1. ノートの概要と記載内容
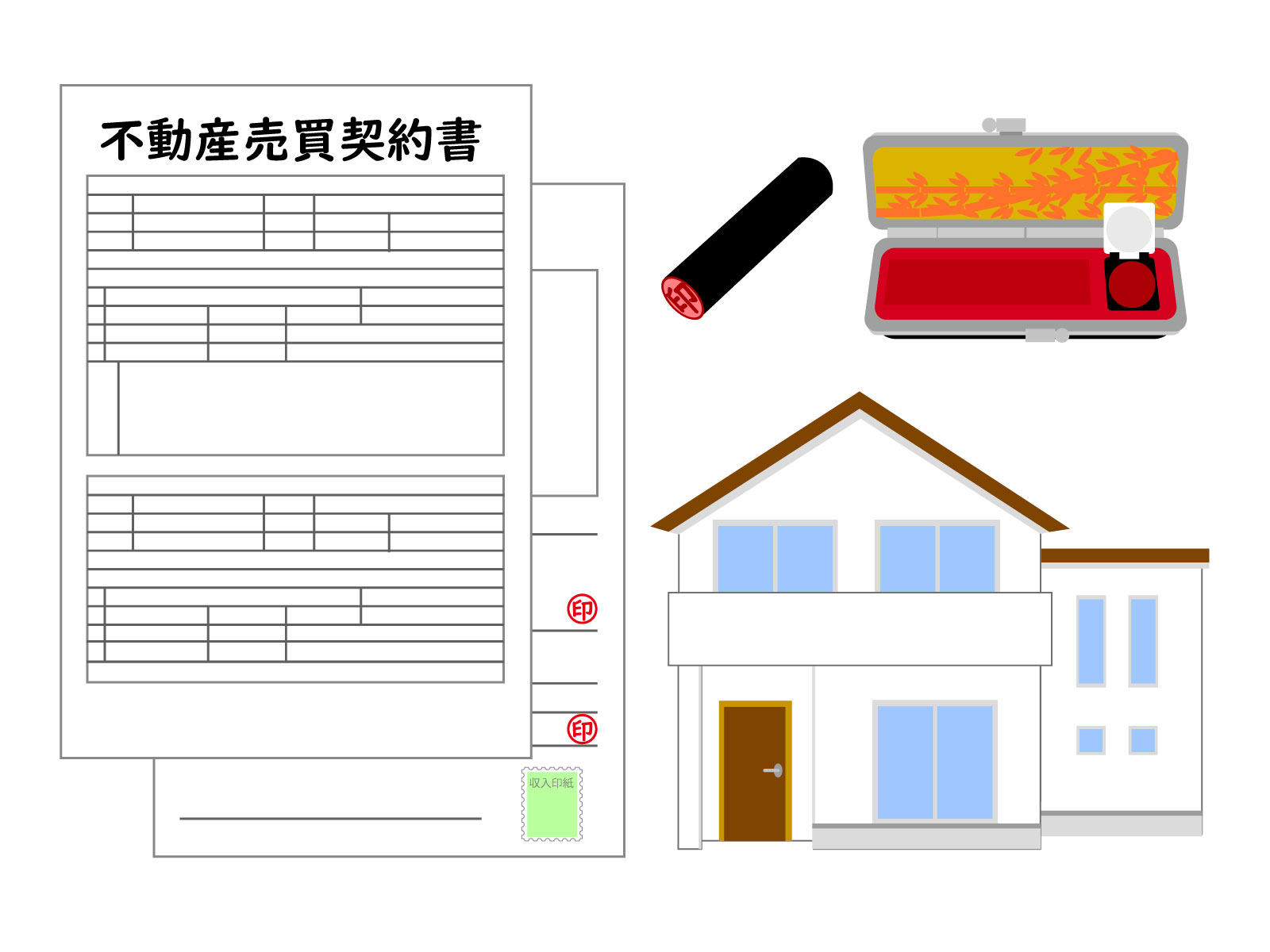
■ ノートの目的と意義
「住まいのエンディングノート」は、以下の目的で活用されます:
・住まいに関する情報や将来の希望を記録し、相続時の混乱を防ぐ。
・住まいの将来を考える際や相続時に参考となる制度や手続き、相談先を掲載し、家族で話し合うきっかけとする。
・空き家問題への対策として、住まいの将来についての意思を明確にする。
■ 主な記載項目
ノートには、以下のような項目を記載します:
・住まいの基本情報:住所、建物の種類、建築年など。
・所有者情報:所有者の氏名、連絡先、相続人の情報など。
・住まいの将来の希望:住み続ける、売却する、賃貸に出すなどの希望。
・修繕・改修の履歴:過去の修繕や改修の内容と時期。
・重要書類の保管場所:登記簿、契約書、遺言書などの保管場所。
・相談先情報:不動産業者、司法書士、行政機関などの連絡先。
これらの情報を記録することで、相続時の手続きがスムーズに進み、空き家の発生を未然に防ぐことができます。
「住まいのエンディングノート」は、家族で住まいの将来について話し合う際の有効なツールとなります。早めに記入を始め、定期的に見直すことで、安心して将来を迎える準備が整います。
「住まいのエンディングノート」は、以下の目的で活用されます:
・住まいに関する情報や将来の希望を記録し、相続時の混乱を防ぐ。
・住まいの将来を考える際や相続時に参考となる制度や手続き、相談先を掲載し、家族で話し合うきっかけとする。
・空き家問題への対策として、住まいの将来についての意思を明確にする。
■ 主な記載項目
ノートには、以下のような項目を記載します:
・住まいの基本情報:住所、建物の種類、建築年など。
・所有者情報:所有者の氏名、連絡先、相続人の情報など。
・住まいの将来の希望:住み続ける、売却する、賃貸に出すなどの希望。
・修繕・改修の履歴:過去の修繕や改修の内容と時期。
・重要書類の保管場所:登記簿、契約書、遺言書などの保管場所。
・相談先情報:不動産業者、司法書士、行政機関などの連絡先。
これらの情報を記録することで、相続時の手続きがスムーズに進み、空き家の発生を未然に防ぐことができます。
「住まいのエンディングノート」は、家族で住まいの将来について話し合う際の有効なツールとなります。早めに記入を始め、定期的に見直すことで、安心して将来を迎える準備が整います。
3-2. 空き家発生の予防策としての効果

「住まいのエンディングノート」は、空き家の発生を未然に防ぐための有効なツールとして注目されています。このノートを活用することで、所有者が生前に住まいや資産についての意思を明確にし、家族や相続人と共有することが可能となります。
■ 家族間の意思疎通を促進
エンディングノートには、住まいの将来に関する希望や、相続に関する情報を記載する項目が含まれています。これにより、家族間での話し合いが促進され、相続時の混乱やトラブルを回避することができます。例えば、越谷市では「住まいの終活ノート」を作成し、住まいの将来について家族で話し合うきっかけを提供しています。
■ 相続登記の促進
空き家の発生要因の一つに、相続登記の未了があります。エンディングノートを活用することで、相続人が必要な情報を把握しやすくなり、相続登記の手続きを円滑に進めることができます。これにより、所有者不明土地の発生を防ぐ効果が期待されます。
■ 自治体との連携による啓発活動
多くの自治体では、エンディングノートを活用したセミナーや相談会を開催し、住民への啓発活動を行っています。例えば、神奈川県では「空き家にしない“わが家”の終活ノート」を作成し、セミナーや相談会を通じて住民への普及を図っています。
このように、「住まいのエンディングノート」は、空き家の発生を未然に防ぐための有効な手段として、個人や自治体での活用が進められています。早期の情報整理と家族間の意思共有が、将来的なトラブルを防ぐ鍵となります。
■ 家族間の意思疎通を促進
エンディングノートには、住まいの将来に関する希望や、相続に関する情報を記載する項目が含まれています。これにより、家族間での話し合いが促進され、相続時の混乱やトラブルを回避することができます。例えば、越谷市では「住まいの終活ノート」を作成し、住まいの将来について家族で話し合うきっかけを提供しています。
■ 相続登記の促進
空き家の発生要因の一つに、相続登記の未了があります。エンディングノートを活用することで、相続人が必要な情報を把握しやすくなり、相続登記の手続きを円滑に進めることができます。これにより、所有者不明土地の発生を防ぐ効果が期待されます。
■ 自治体との連携による啓発活動
多くの自治体では、エンディングノートを活用したセミナーや相談会を開催し、住民への啓発活動を行っています。例えば、神奈川県では「空き家にしない“わが家”の終活ノート」を作成し、セミナーや相談会を通じて住民への普及を図っています。
このように、「住まいのエンディングノート」は、空き家の発生を未然に防ぐための有効な手段として、個人や自治体での活用が進められています。早期の情報整理と家族間の意思共有が、将来的なトラブルを防ぐ鍵となります。
4. 実際の活用事例と成果
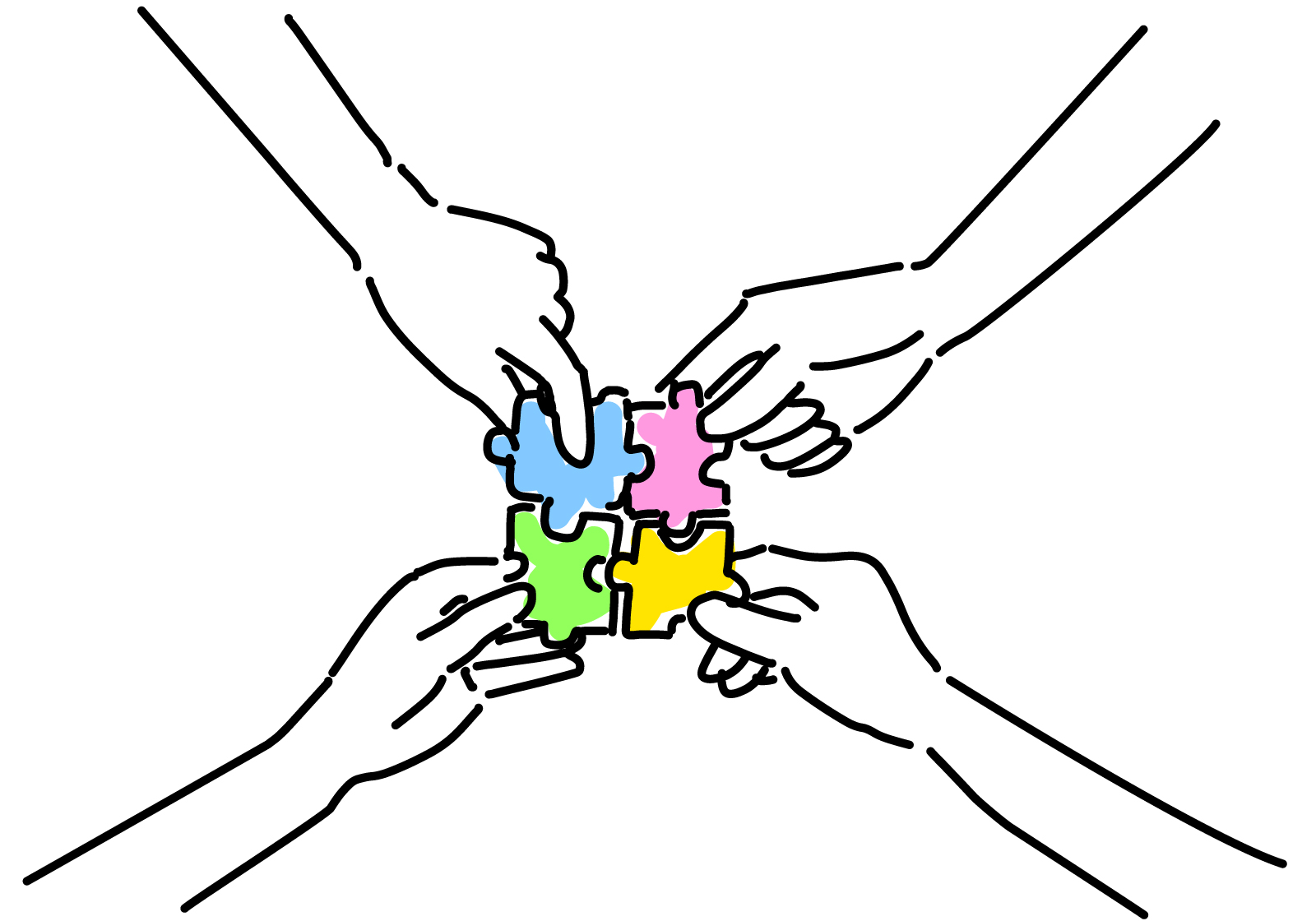
4-1. 自治体によるノートの導入事例

「住まいのエンディングノート」は、空き家対策や相続問題の予防策として、全国の自治体で導入が進められています。以下に、いくつかの自治体での導入事例を紹介します。
■ 埼玉県越谷市:「住まいの終活ノート」の配布
越谷市では、住まいの将来について考えるきっかけとして「住まいの終活ノート」を作成し、市民に配布しています。このノートには、住まいの基本情報、所有者情報、将来の希望、修繕履歴、重要書類の保管場所、相談先情報などを記載する項目が含まれており、家族での話し合いを促進するツールとして活用されています。
■ 神奈川県:「空き家にしない“わが家”の終活ノート」の活用
神奈川県では、「空き家にしない“わが家”の終活ノート」を作成し、県民に配布しています。このノートは、住まいの将来についての希望や相続に関する情報を記録することで、空き家の発生を未然に防ぐことを目的としています。また、ノートの活用を促進するためのセミナーや相談会も開催されています。
■ その他の自治体での取り組み
他の自治体でも、住まいのエンディングノートの導入が進められています。例えば、東京都や大阪府などの都市部では、高齢化や人口減少に伴う空き家問題への対策として、住まいの将来について考えるためのノートを作成・配布しています。これらのノートは、住民が自らの住まいについて考え、家族と話し合うきっかけとなることを目的としています。
これらの導入事例からも分かるように、「住まいのエンディングノート」は、空き家問題の予防策として有効な手段となっています。自治体による積極的な導入と普及活動が、今後の空き家対策において重要な役割を果たすことが期待されます。
■ 埼玉県越谷市:「住まいの終活ノート」の配布
越谷市では、住まいの将来について考えるきっかけとして「住まいの終活ノート」を作成し、市民に配布しています。このノートには、住まいの基本情報、所有者情報、将来の希望、修繕履歴、重要書類の保管場所、相談先情報などを記載する項目が含まれており、家族での話し合いを促進するツールとして活用されています。
■ 神奈川県:「空き家にしない“わが家”の終活ノート」の活用
神奈川県では、「空き家にしない“わが家”の終活ノート」を作成し、県民に配布しています。このノートは、住まいの将来についての希望や相続に関する情報を記録することで、空き家の発生を未然に防ぐことを目的としています。また、ノートの活用を促進するためのセミナーや相談会も開催されています。
■ その他の自治体での取り組み
他の自治体でも、住まいのエンディングノートの導入が進められています。例えば、東京都や大阪府などの都市部では、高齢化や人口減少に伴う空き家問題への対策として、住まいの将来について考えるためのノートを作成・配布しています。これらのノートは、住民が自らの住まいについて考え、家族と話し合うきっかけとなることを目的としています。
これらの導入事例からも分かるように、「住まいのエンディングノート」は、空き家問題の予防策として有効な手段となっています。自治体による積極的な導入と普及活動が、今後の空き家対策において重要な役割を果たすことが期待されます。
4-2. ノート活用による空き家減少の成果

「住まいのエンディングノート」は、空き家の発生を未然に防ぐための有効なツールとして、自治体による導入が進められています。以下に、具体的な成果を挙げた事例を紹介します。
■ 神奈川県の取り組み
神奈川県では、高齢化の進行に伴い、将来的な空き家の増加が懸念されています。この課題に対応するため、同県は「空き家にしない“わが家”の終活ノート」を作成し、住民に配布しました。このノートは、住まいの将来についての希望や相続に関する情報を記録することで、空き家の発生を未然に防ぐことを目的としています。また、ノートの活用を促進するためのセミナーや相談会も開催され、住民の意識啓発に寄与しています。
■ 東京都の取り組み
東京都では、高齢者への空き家抑制意識の啓発と支援を目的に、終活支援事業者監修によるオリジナルエンディングノート「私と家 これからノート」を制作しました。このノートは、住まいの将来設計を立てるための新たなツールとして、セミナーや勉強会で無料配布され、書き込みながら受講することで、住まいにおける情報整理を共にサポートしています。
■ 松本市の取り組み
長野県松本市では、65歳以上の高齢者のみの世帯が住む住宅を「空家予備軍」と捉え、対策を打つことで空家発生の未然予防に繋げています。その一環として、「住まいの終活ノート(エンディングノート)」を活用し、空家予備軍に対して住まいの将来について考えるきっかけを提供しています。
これらの事例からも分かるように、「住まいのエンディングノート」は、空き家の発生を未然に防ぐための有効な手段として、自治体による導入と普及活動が進められています。住民が自らの住まいについて考え、家族と話し合うきっかけとなることで、将来的な空き家の発生を抑制する効果が期待されています。
■ 神奈川県の取り組み
神奈川県では、高齢化の進行に伴い、将来的な空き家の増加が懸念されています。この課題に対応するため、同県は「空き家にしない“わが家”の終活ノート」を作成し、住民に配布しました。このノートは、住まいの将来についての希望や相続に関する情報を記録することで、空き家の発生を未然に防ぐことを目的としています。また、ノートの活用を促進するためのセミナーや相談会も開催され、住民の意識啓発に寄与しています。
■ 東京都の取り組み
東京都では、高齢者への空き家抑制意識の啓発と支援を目的に、終活支援事業者監修によるオリジナルエンディングノート「私と家 これからノート」を制作しました。このノートは、住まいの将来設計を立てるための新たなツールとして、セミナーや勉強会で無料配布され、書き込みながら受講することで、住まいにおける情報整理を共にサポートしています。
■ 松本市の取り組み
長野県松本市では、65歳以上の高齢者のみの世帯が住む住宅を「空家予備軍」と捉え、対策を打つことで空家発生の未然予防に繋げています。その一環として、「住まいの終活ノート(エンディングノート)」を活用し、空家予備軍に対して住まいの将来について考えるきっかけを提供しています。
これらの事例からも分かるように、「住まいのエンディングノート」は、空き家の発生を未然に防ぐための有効な手段として、自治体による導入と普及活動が進められています。住民が自らの住まいについて考え、家族と話し合うきっかけとなることで、将来的な空き家の発生を抑制する効果が期待されています。
5. 今後の展望と提言

5-1. 行政と住民の連携強化の必要性

空き家問題の深刻化に伴い、行政と住民が連携して対策を講じることの重要性が増しています。特に、地域の実情に即した取り組みを進めるためには、双方の協力が不可欠です。
■ 地域住民との協働による効果的な対策
行政が単独で空き家対策を行うには限界があります。地域住民と協働することで、空き家の実態把握や適切な管理が可能となり、効果的な対策が実現します。
■ 住民主体の取り組みの促進
住民が主体となって空き家対策に取り組むことで、地域の課題に対する意識が高まり、持続可能な対策が可能となります。例えば、自治会やNPOが中心となって空き家の活用を進める事例も見られます。
■ 情報共有と意識啓発の強化
行政と住民が情報を共有し、空き家問題に対する意識を高めることが、連携強化の第一歩です。セミナーや相談会を通じて、双方の理解を深めることが求められます。
このように、行政と住民が連携して空き家対策に取り組むことが、地域の持続的な発展に寄与します。
■ 地域住民との協働による効果的な対策
行政が単独で空き家対策を行うには限界があります。地域住民と協働することで、空き家の実態把握や適切な管理が可能となり、効果的な対策が実現します。
■ 住民主体の取り組みの促進
住民が主体となって空き家対策に取り組むことで、地域の課題に対する意識が高まり、持続可能な対策が可能となります。例えば、自治会やNPOが中心となって空き家の活用を進める事例も見られます。
■ 情報共有と意識啓発の強化
行政と住民が情報を共有し、空き家問題に対する意識を高めることが、連携強化の第一歩です。セミナーや相談会を通じて、双方の理解を深めることが求められます。
このように、行政と住民が連携して空き家対策に取り組むことが、地域の持続的な発展に寄与します。
5-2. 「住まいのエンディングノート」の普及促進策

「住まいのエンディングノート」は、空き家の発生を未然に防ぐための有効なツールとして、自治体や関係機関による普及が進められています。以下に、具体的な普及促進策を紹介します。
■ 自治体によるノートの配布と啓発活動
多くの自治体では、住民に対して「住まいのエンディングノート」を配布し、住まいの将来について考えるきっかけを提供しています。例えば、茨城県東海村では、住まいを所有・管理する住民に対してノートを配布し、家族や親族間での話し合いを促しています。
■ セミナーや相談会の開催
ノートの活用方法や空き家対策について理解を深めるため、セミナーや相談会が各地で開催されています。全国空き家対策推進協議会は、司法書士による空き家対策セミナーをオンラインで開催し、ノートの活用方法を紹介しています。
■ オンラインでのダウンロード提供
国土交通省や各自治体のウェブサイトでは、「住まいのエンディングノート」をPDF形式で提供しており、誰でも自由にダウンロードして利用することができます。これにより、広範な普及が期待されています。
これらの取り組みにより、「住まいのエンディングノート」の普及が進み、空き家の発生を抑制する効果が期待されています。住民一人ひとりが住まいの将来について考え、家族と共有することが、地域全体の空き家対策につながります。
■ 自治体によるノートの配布と啓発活動
多くの自治体では、住民に対して「住まいのエンディングノート」を配布し、住まいの将来について考えるきっかけを提供しています。例えば、茨城県東海村では、住まいを所有・管理する住民に対してノートを配布し、家族や親族間での話し合いを促しています。
■ セミナーや相談会の開催
ノートの活用方法や空き家対策について理解を深めるため、セミナーや相談会が各地で開催されています。全国空き家対策推進協議会は、司法書士による空き家対策セミナーをオンラインで開催し、ノートの活用方法を紹介しています。
■ オンラインでのダウンロード提供
国土交通省や各自治体のウェブサイトでは、「住まいのエンディングノート」をPDF形式で提供しており、誰でも自由にダウンロードして利用することができます。これにより、広範な普及が期待されています。
これらの取り組みにより、「住まいのエンディングノート」の普及が進み、空き家の発生を抑制する効果が期待されています。住民一人ひとりが住まいの将来について考え、家族と共有することが、地域全体の空き家対策につながります。
