2025年4月の建築基準法改正により、「4号特例」が縮小され、リフォームや増改築における手続きや要件が大きく変わります。これまで確認申請が不要だった木造2階建て住宅の大規模リフォームでも、今後は建築確認申請が必要となるケースが増加し、計画や費用、工期に影響を及ぼす可能性があります。本記事では、改正のポイントやリフォームへの影響、注意点について詳しく解説します。

1. 建築基準法改正と4号特例の縮小

1-1. 4号特例とは何か?

「4号特例」とは、建築基準法第6条第1項第4号に基づき、特定の小規模建築物に対して建築確認申請の一部審査を省略できる制度です。この特例は、1983年に導入され、主に以下のような条件を満たす木造建築物が対象となります:
・2階建て以下
・延べ面積500㎡以下
・高さ13m以下
・軒高9m以下
この制度の目的は、建築確認申請の手続きを簡素化し、建築士が設計・監理を行うことで、構造関係規定や防火避難規定などの一部審査を省略することです。これにより、設計や施工の効率化が図られ、住宅建設の促進が期待されました。
・2階建て以下
・延べ面積500㎡以下
・高さ13m以下
・軒高9m以下
この制度の目的は、建築確認申請の手続きを簡素化し、建築士が設計・監理を行うことで、構造関係規定や防火避難規定などの一部審査を省略することです。これにより、設計や施工の効率化が図られ、住宅建設の促進が期待されました。
1-2. 改正の背景と目的

2025年4月施行建築基準法の改正により、「4号特例」の適用範囲が縮小される背景には、主に以下の2つの目的があります。
1. 住宅の省エネ化促進
政府は2050年までにカーボンニュートラルを実現する目標を掲げており、その一環として建築物の省エネルギー性能の向上が求められています。これまで4号特例の対象となっていた小規模な木造住宅は、省エネ基準の適合確認が免除されていたため、全体の省エネ化に支障をきたしていました。今回の改正により、これらの建物も省エネ基準への適合が義務付けられ、建築確認申請時に省エネ性能の審査が行われるようになります。
2. 建築物の安全性向上
近年、地震や台風などの自然災害が頻発しており、建築物の安全性確保が重要な課題となっています。4号特例のもとでは、構造計算の審査が省略されることが多く、結果として耐震性や耐風性に問題のある建物が存在する可能性が指摘されていました。改正後は、これらの建物についても構造計算の審査が義務付けられ、建築物の安全性がより厳格に確認されるようになります。
このように、4号特例の縮小は、省エネルギー性能の向上と建築物の安全性確保という2つの観点から、建築物の質を高めることを目的としています。
1. 住宅の省エネ化促進
政府は2050年までにカーボンニュートラルを実現する目標を掲げており、その一環として建築物の省エネルギー性能の向上が求められています。これまで4号特例の対象となっていた小規模な木造住宅は、省エネ基準の適合確認が免除されていたため、全体の省エネ化に支障をきたしていました。今回の改正により、これらの建物も省エネ基準への適合が義務付けられ、建築確認申請時に省エネ性能の審査が行われるようになります。
2. 建築物の安全性向上
近年、地震や台風などの自然災害が頻発しており、建築物の安全性確保が重要な課題となっています。4号特例のもとでは、構造計算の審査が省略されることが多く、結果として耐震性や耐風性に問題のある建物が存在する可能性が指摘されていました。改正後は、これらの建物についても構造計算の審査が義務付けられ、建築物の安全性がより厳格に確認されるようになります。
このように、4号特例の縮小は、省エネルギー性能の向上と建築物の安全性確保という2つの観点から、建築物の質を高めることを目的としています。
2. リフォームへの影響

2-1. 確認申請が必要となるリフォームとは?

2025年4月の建築基準法改正により、これまで確認申請が不要だったリフォーム工事の一部が、新たに申請対象となります。特に「新2号建築物」に該当する木造2階建て住宅や延床面積200㎡を超える木造平屋建て住宅では、以下のようなリフォーム工事で建築確認申請が必要になります。
確認申請が必要となるリフォームの例
・主要構造部の過半を改修する工事
壁、柱、床、梁、屋根、階段などの主要構造部の50%を超える修繕や模様替え(例:スケルトンリフォーム、屋根の葺き替え、外壁の張り替え)
・間取りの大幅な変更
居室や廊下、玄関、階段などの位置変更や、階段の架け替えなど
増築や改築工事
建物の床面積を増やす増築や、建物の一部を解体して再建築する改築
一方で、以下のような小規模なリフォーム工事は、引き続き確認申請が不要です。
確認申請が不要なリフォームの例
・キッチン、トイレ、浴室などの水回り設備の交換
・壁紙や床材の張り替え
・手すりやスロープの設置などのバリアフリー改修
ただし、確認申請が不要な工事であっても、建築基準法に適合している必要があります。特に、省エネルギー性能や耐震性能の確保が求められるため、リフォーム計画時には注意が必要です。
確認申請が必要となるリフォームの例
・主要構造部の過半を改修する工事
壁、柱、床、梁、屋根、階段などの主要構造部の50%を超える修繕や模様替え(例:スケルトンリフォーム、屋根の葺き替え、外壁の張り替え)
・間取りの大幅な変更
居室や廊下、玄関、階段などの位置変更や、階段の架け替えなど
増築や改築工事
建物の床面積を増やす増築や、建物の一部を解体して再建築する改築
一方で、以下のような小規模なリフォーム工事は、引き続き確認申請が不要です。
確認申請が不要なリフォームの例
・キッチン、トイレ、浴室などの水回り設備の交換
・壁紙や床材の張り替え
・手すりやスロープの設置などのバリアフリー改修
ただし、確認申請が不要な工事であっても、建築基準法に適合している必要があります。特に、省エネルギー性能や耐震性能の確保が求められるため、リフォーム計画時には注意が必要です。
2-2. 再建築不可物件への影響

2025年4月の建築基準法改正により、再建築不可物件のリフォームには大きな影響が生じます。これまで「4号特例」により建築確認申請が不要だった小規模建築物も、新たに「新2号建築物」に分類され、確認申請が必要となるケースが増加します。特に、主要構造部の過半を改修するような大規模リフォーム(例:屋根の葺き替え、外壁の全面張り替え、柱や梁の交換など)は、建築確認申請の対象となります。
再建築不可物件は、接道義務を満たしていないため、建築確認申請が通らず、大規模なリフォームが実質的に困難になる可能性があります。また、耐震性や省エネルギー性能など、現行の建築基準法に適合させるための改修が求められ、費用や技術的なハードルが高くなります。
このような状況下では、壁紙や床材の張り替え、設備の交換など、構造に影響を与えない小規模なリフォームにとどめるか、専門の不動産会社への売却を検討することが現実的な選択肢となります。再建築不可物件の所有者は、法改正の内容を十分に理解し、早めに専門家へ相談することが重要です。
再建築不可物件は、接道義務を満たしていないため、建築確認申請が通らず、大規模なリフォームが実質的に困難になる可能性があります。また、耐震性や省エネルギー性能など、現行の建築基準法に適合させるための改修が求められ、費用や技術的なハードルが高くなります。
このような状況下では、壁紙や床材の張り替え、設備の交換など、構造に影響を与えない小規模なリフォームにとどめるか、専門の不動産会社への売却を検討することが現実的な選択肢となります。再建築不可物件の所有者は、法改正の内容を十分に理解し、早めに専門家へ相談することが重要です。
3. リフォーム計画の見直しポイント

3-1. 工期とコストの増加に注意
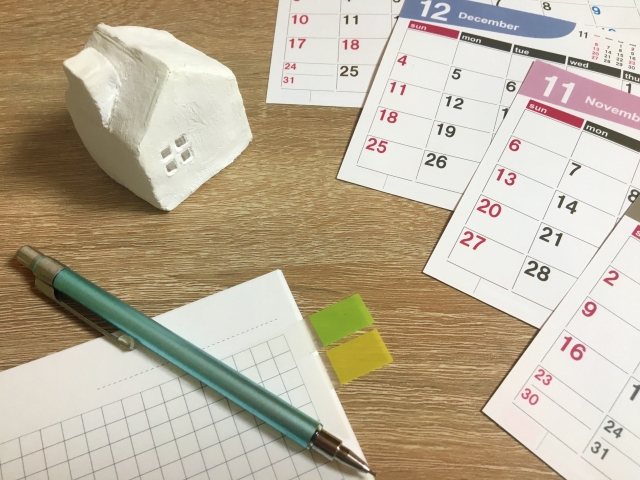
2025年4月の建築基準法改正により、「4号特例」の縮小が実施され、これまで確認申請が不要だった小規模な木造住宅のリフォームにも、建築確認申請が必要となるケースが増加します。
1.工期の延長
建築確認申請の手続きが増加し、審査項目の増加や提出図書の追加により、設計から施工までの全体的な工期は長期化が予想されます。確認申請から着工までの期間が延びることで、年間の施工件数にも影響を与えるでしょう。
2.コストの増加
建築確認申請にかかる手数料や設計費用、省エネ基準適合のための追加費用、工期の長期化によるコスト増加が懸念されます。
これらの影響を受け、リフォーム計画を立てる際には、工期やコストの増加を考慮し、事前に専門家と相談することが重要です。
1.工期の延長
建築確認申請の手続きが増加し、審査項目の増加や提出図書の追加により、設計から施工までの全体的な工期は長期化が予想されます。確認申請から着工までの期間が延びることで、年間の施工件数にも影響を与えるでしょう。
2.コストの増加
建築確認申請にかかる手数料や設計費用、省エネ基準適合のための追加費用、工期の長期化によるコスト増加が懸念されます。
これらの影響を受け、リフォーム計画を立てる際には、工期やコストの増加を考慮し、事前に専門家と相談することが重要です。
3-2. 省エネ基準への対応

2025年4月施行の建築基準法および建築物省エネ法の改正により、増改築時の省エネ基準への適合が義務化されます。これにより、リフォーム計画においても省エネ性能の確保が重要な要素となります。
省エネ基準適合のポイント
・対象となる工事:増改築部分の床面積が10㎡を超える場合、省エネ基準への適合が求められます。
・適合範囲:改正前は建築物全体が適合対象でしたが、改正後は増改築を行う部分のみが対象となります。
・適合方法:外皮性能基準(断熱性能)や一次エネルギー消費量基準に基づき、増改築部分の性能を評価します。
リフォーム計画への影響
省エネ基準への適合義務化により、以下の点に注意が必要です:
・設計の工夫:断熱材の選定や設備機器の性能向上など、省エネ性能を確保するための設計が求められます。
・コストの増加:高性能な建材や設備の導入により、リフォーム費用が増加する可能性があります。
・手続きの複雑化:省エネ適合性判定のための申請や審査が必要となり、手続きが複雑になることが予想されます。
リフォームを検討する際は、これらの点を踏まえ、専門家と相談しながら計画を進めることが重要です。
省エネ基準適合のポイント
・対象となる工事:増改築部分の床面積が10㎡を超える場合、省エネ基準への適合が求められます。
・適合範囲:改正前は建築物全体が適合対象でしたが、改正後は増改築を行う部分のみが対象となります。
・適合方法:外皮性能基準(断熱性能)や一次エネルギー消費量基準に基づき、増改築部分の性能を評価します。
リフォーム計画への影響
省エネ基準への適合義務化により、以下の点に注意が必要です:
・設計の工夫:断熱材の選定や設備機器の性能向上など、省エネ性能を確保するための設計が求められます。
・コストの増加:高性能な建材や設備の導入により、リフォーム費用が増加する可能性があります。
・手続きの複雑化:省エネ適合性判定のための申請や審査が必要となり、手続きが複雑になることが予想されます。
リフォームを検討する際は、これらの点を踏まえ、専門家と相談しながら計画を進めることが重要です。
4. 業者選定の重要性

4-1. 確認申請に対応できる業者の選定

2025年4月の建築基準法改正により、リフォームにおける「4号特例」の縮小が実施され、建築確認申請が必要なケースが増加します。これに伴い、確認申請に対応できる信頼性の高い業者の選定がこれまで以上に重要となります。以下に、業者選定の際に注目すべきポイントをまとめました。
✅ 確認申請対応業者を選ぶ際のチェックポイント
1. 確認申請の実績と対応力
・過去に建築確認申請を含むリフォーム工事の実績が豊富な業者を選びましょう。
・申請手続きの代行やサポートが可能かを確認することが重要です。
2. 建築士の在籍と法令知識
・一級または二級建築士が在籍しているかを確認しましょう。
・最新の建築基準法や地方自治体の条例に精通しているかも重要なポイントです。
3. 施工実績と評判
・過去の施工事例を確認し、特に確認申請が必要なリフォームの経験があるかをチェックしましょう。
・顧客からの評判や口コミも参考になります。
4. 見積もりの透明性
・建築確認申請にかかる費用が明確に示されているかを確認しましょう。
・追加費用の有無やその条件についても事前に把握しておくことが大切です。
5. アフターサービスと保証内容
・工事後のアフターサービスや保証内容が充実しているかを確認しましょう。
・定期点検やメンテナンスの体制が整っている業者は安心です。
これらのポイントを踏まえ、複数の業者から見積もりを取り、比較検討することをおすすめします。信頼できる業者を選定することで、リフォーム工事をスムーズに進めることができます
✅ 確認申請対応業者を選ぶ際のチェックポイント
1. 確認申請の実績と対応力
・過去に建築確認申請を含むリフォーム工事の実績が豊富な業者を選びましょう。
・申請手続きの代行やサポートが可能かを確認することが重要です。
2. 建築士の在籍と法令知識
・一級または二級建築士が在籍しているかを確認しましょう。
・最新の建築基準法や地方自治体の条例に精通しているかも重要なポイントです。
3. 施工実績と評判
・過去の施工事例を確認し、特に確認申請が必要なリフォームの経験があるかをチェックしましょう。
・顧客からの評判や口コミも参考になります。
4. 見積もりの透明性
・建築確認申請にかかる費用が明確に示されているかを確認しましょう。
・追加費用の有無やその条件についても事前に把握しておくことが大切です。
5. アフターサービスと保証内容
・工事後のアフターサービスや保証内容が充実しているかを確認しましょう。
・定期点検やメンテナンスの体制が整っている業者は安心です。
これらのポイントを踏まえ、複数の業者から見積もりを取り、比較検討することをおすすめします。信頼できる業者を選定することで、リフォーム工事をスムーズに進めることができます
4-2. 契約前の詳細な打ち合わせ

建築確認申請前の打ち合わせは、リフォーム計画を円滑に進めるための重要なステップです。以下に、契約前に行うべき詳細な打ち合わせのポイントをまとめました。
✅ 契約前の詳細な打ち合わせのポイント
1. 設計内容の確定
・建築確認申請後は、設計や間取りの変更が原則としてできません。
・申請前に、設計や間取り・設備等を施工業者やハウスメーカーの担当者と念入りに打ち合わせを行い、納得することが重要です。
2. 見積もりの明確化
・見積書の各項目が、建物のどの部分の費用に該当するのかを明確に把握しましょう。
・不明な点は、遠慮せず、後に残さず確認することが大切です。
3. 法的要件の確認
・建築基準法や地方自治体の条例に適合しているかを確認するため、必要な書類や手続きを事前に把握しておきましょう。
・申請に必要な書類が不備の場合、審査がスムーズに進まず、場合によっては申請が拒否されることもあります。
4. スケジュールの調整
・建築確認申請の審査期間や、工事の着工・完了までのスケジュールを事前に確認し、計画的に進めることが重要です。
5. 変更時の対応策の確認
・建築確認申請後に変更点が出た場合は、「計画変更の申請」を行い、変更点が法律に適合しているかの審査が改めて必要です。
・費用や工数が多くかさみ、施工スケジュールも伸びてしまう可能性があるため、事前に対応策を確認しておきましょう。
これらのポイントを踏まえ、契約前に施工業者や設計者と十分な打ち合わせを行うことで、リフォーム計画をスムーズに進めることができます。
✅ 契約前の詳細な打ち合わせのポイント
1. 設計内容の確定
・建築確認申請後は、設計や間取りの変更が原則としてできません。
・申請前に、設計や間取り・設備等を施工業者やハウスメーカーの担当者と念入りに打ち合わせを行い、納得することが重要です。
2. 見積もりの明確化
・見積書の各項目が、建物のどの部分の費用に該当するのかを明確に把握しましょう。
・不明な点は、遠慮せず、後に残さず確認することが大切です。
3. 法的要件の確認
・建築基準法や地方自治体の条例に適合しているかを確認するため、必要な書類や手続きを事前に把握しておきましょう。
・申請に必要な書類が不備の場合、審査がスムーズに進まず、場合によっては申請が拒否されることもあります。
4. スケジュールの調整
・建築確認申請の審査期間や、工事の着工・完了までのスケジュールを事前に確認し、計画的に進めることが重要です。
5. 変更時の対応策の確認
・建築確認申請後に変更点が出た場合は、「計画変更の申請」を行い、変更点が法律に適合しているかの審査が改めて必要です。
・費用や工数が多くかさみ、施工スケジュールも伸びてしまう可能性があるため、事前に対応策を確認しておきましょう。
これらのポイントを踏まえ、契約前に施工業者や設計者と十分な打ち合わせを行うことで、リフォーム計画をスムーズに進めることができます。
5. 今後のリフォーム戦略

5-1. 小規模リフォームの検討

2025年4月の建築基準法改正により、「4号特例」の縮小が実施されましたが、小規模なリフォームについては、引き続き建築確認申請が不要なケースが多く存在します。以下に、小規模リフォームの検討に際してのポイントをまとめました。
1. 建築確認申請が不要なリフォーム
以下のような工事は、建物の構造や安全性に大きな影響を与えないため、原則として建築確認申請は不要です。
・増築(部屋の増築、物置・倉庫やカーポート・ガレージの設置など)
・屋根の葺き替え・カバー工法(「4号建築物」以外)
・外壁の全体改修(「4号建築物」以外)
・リノベーション・スケルトンリフォーム(「4号建築物」以外)
2. 建築確認申請が必要なリフォーム
以下のような工事は、建物の主要構造部に関わるため、建築確認申請が必要となります。
・増築(部屋の増築、物置・倉庫やカーポート・ガレージの設置など)
・屋根の葺き替え・カバー工法(「4号建築物」以外)
・外壁の全体改修(「4号建築物」以外)
・リノベーション・スケルトンリフォーム(「4号建築物」以外)
3. 注意点
・建築確認申請が不要な場合でも、リフォーム後の建築物は建築基準法の規定に適合している必要があります。
・リフォームの内容によっては、省エネルギー性能や耐震性能の確保が求められる場合があります。
小規模なリフォームを検討する際は、建築確認申請の要否を事前に確認し、適切な手続きを行うことが重要です。また、リフォーム後の建物が建築基準法に適合していることを確認するため、専門家への相談をおすすめします。
1. 建築確認申請が不要なリフォーム
以下のような工事は、建物の構造や安全性に大きな影響を与えないため、原則として建築確認申請は不要です。
・増築(部屋の増築、物置・倉庫やカーポート・ガレージの設置など)
・屋根の葺き替え・カバー工法(「4号建築物」以外)
・外壁の全体改修(「4号建築物」以外)
・リノベーション・スケルトンリフォーム(「4号建築物」以外)
2. 建築確認申請が必要なリフォーム
以下のような工事は、建物の主要構造部に関わるため、建築確認申請が必要となります。
・増築(部屋の増築、物置・倉庫やカーポート・ガレージの設置など)
・屋根の葺き替え・カバー工法(「4号建築物」以外)
・外壁の全体改修(「4号建築物」以外)
・リノベーション・スケルトンリフォーム(「4号建築物」以外)
3. 注意点
・建築確認申請が不要な場合でも、リフォーム後の建築物は建築基準法の規定に適合している必要があります。
・リフォームの内容によっては、省エネルギー性能や耐震性能の確保が求められる場合があります。
小規模なリフォームを検討する際は、建築確認申請の要否を事前に確認し、適切な手続きを行うことが重要です。また、リフォーム後の建物が建築基準法に適合していることを確認するため、専門家への相談をおすすめします。
5-2. 補助金や支援制度の活用

建築基準法の改正に伴い、リフォーム計画においても補助金や支援制度の活用が重要となっています。以下に、リフォームに関連する主な補助金制度とその活用方法をまとめました。
✅ リフォームに活用できる主な補助金・支援制度
1. 小規模事業者持続化補助金
・概要: 小規模事業者が行う販路開拓や業務効率化の取り組みに対して、経費の一部を補助する制度です。
・助額・率: 最大250万円、補助率2/3。
・活用例: リフォーム業者が新たなサービスを提供するための設備導入や、広告宣伝費用などに利用されています。
2. ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
・概要: 中小企業等が行う革新的なサービス開発や生産プロセスの改善を支援する制度です。
・補助額・率: 最大3,000万円、補助率1/2~2/3。
・活用例: リフォーム業者が最新の省エネ設備を導入する際の費用補助などに利用されています。
3. IT導入補助金
・概要: 中小企業等がITツールを導入する際の経費の一部を補助する制度です。
・補助額・率: 最大450万円、補助率1/2~4/5。
・活用例: リフォーム業者が業務効率化のためのソフトウェア導入や、顧客管理システムの導入などに利用されています。
✅ 補助金活用のポイント
1.最新情報の確認: 補助金制度は年度ごとに内容が変更されることがあるため、常に最新の情報を確認しましょう。
2.専門家への相談: 商工会議所や中小企業診断士などの専門家に相談することで、適切な補助金の選定や申請書類の作成支援を受けることができます。
3.計画的な申請: 補助金の申請には時間がかかる場合があるため、リフォーム計画と並行して早めに準備を始めることが重要です。
これらの補助金や支援制度を活用することで、リフォームにかかる費用の負担を軽減し、より効果的なリフォーム計画を実現することが可能です。具体的な制度の詳細や申請方法については、各制度の公式サイトや専門家に相談することをおすすめします。
✅ リフォームに活用できる主な補助金・支援制度
1. 小規模事業者持続化補助金
・概要: 小規模事業者が行う販路開拓や業務効率化の取り組みに対して、経費の一部を補助する制度です。
・助額・率: 最大250万円、補助率2/3。
・活用例: リフォーム業者が新たなサービスを提供するための設備導入や、広告宣伝費用などに利用されています。
2. ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
・概要: 中小企業等が行う革新的なサービス開発や生産プロセスの改善を支援する制度です。
・補助額・率: 最大3,000万円、補助率1/2~2/3。
・活用例: リフォーム業者が最新の省エネ設備を導入する際の費用補助などに利用されています。
3. IT導入補助金
・概要: 中小企業等がITツールを導入する際の経費の一部を補助する制度です。
・補助額・率: 最大450万円、補助率1/2~4/5。
・活用例: リフォーム業者が業務効率化のためのソフトウェア導入や、顧客管理システムの導入などに利用されています。
✅ 補助金活用のポイント
1.最新情報の確認: 補助金制度は年度ごとに内容が変更されることがあるため、常に最新の情報を確認しましょう。
2.専門家への相談: 商工会議所や中小企業診断士などの専門家に相談することで、適切な補助金の選定や申請書類の作成支援を受けることができます。
3.計画的な申請: 補助金の申請には時間がかかる場合があるため、リフォーム計画と並行して早めに準備を始めることが重要です。
これらの補助金や支援制度を活用することで、リフォームにかかる費用の負担を軽減し、より効果的なリフォーム計画を実現することが可能です。具体的な制度の詳細や申請方法については、各制度の公式サイトや専門家に相談することをおすすめします。
